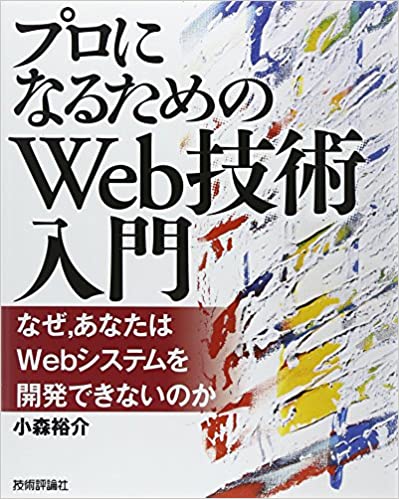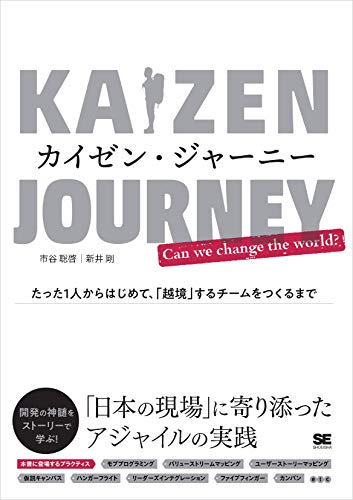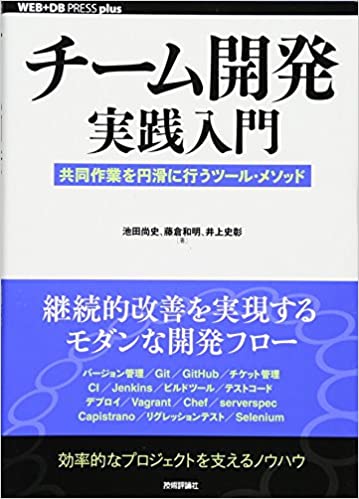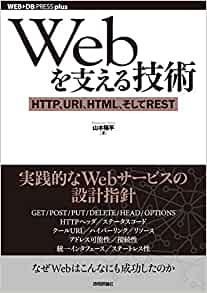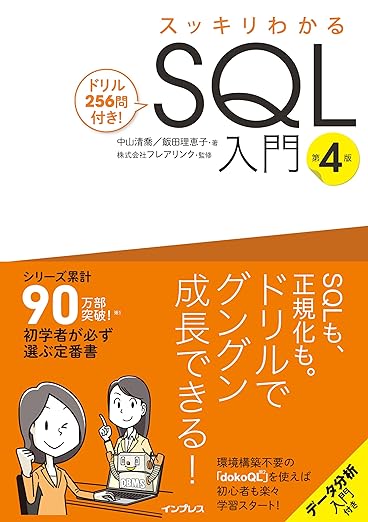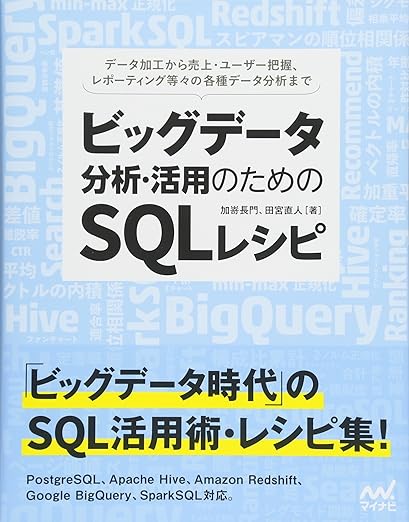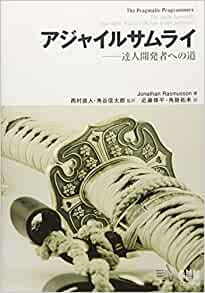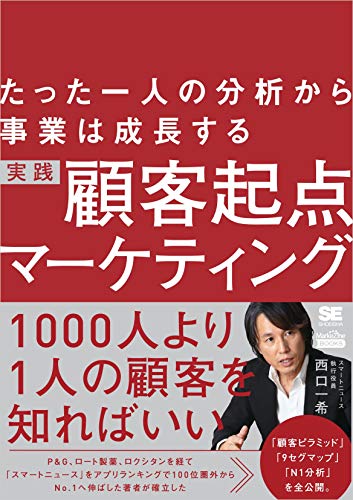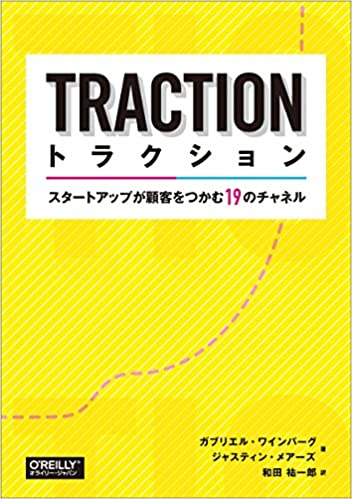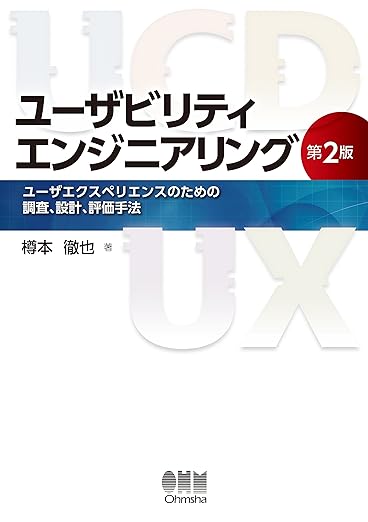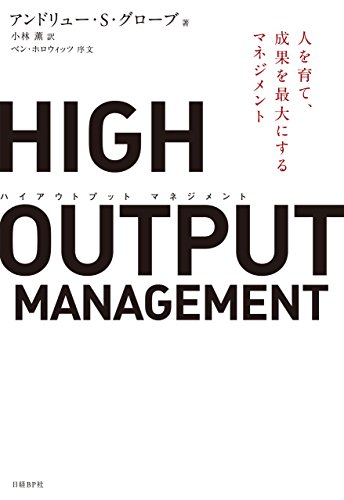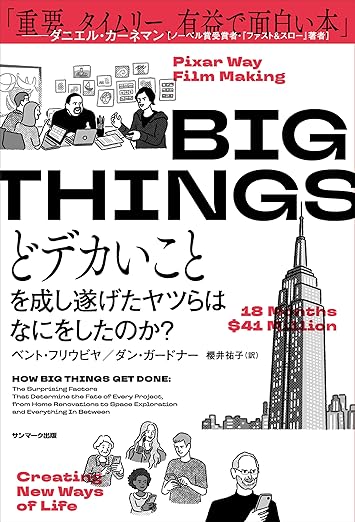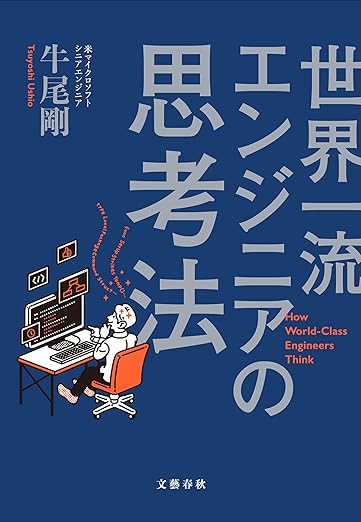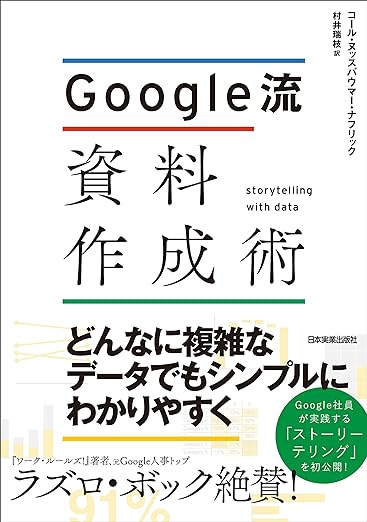現役PdMが厳選!プロダクトマネジメントのおすすめ本

某大手テック企業でプロダクトマネージャー(PdM・PM)をしている若狭です。年齢も重ねてそれなりにシニアなポジションになってきました。
メガベンチャーという性質上、未経験の若手でも育成を見据えてプロダクトマネジメント組織にアサインされるのですが、「プロダクトマネジメントを学ぶには、どんな本がおすすめですか?」「プロダクトマネージャー(PdM)になりたいのですが、書籍は何を読んだらいいですか?」など、後輩や同僚たちから聞かれることが増えてきました。
自分もプロダクトマネージャーになる前やなりたてのころは、右も左も分からなかったので、とにかく諸先輩方がおすすめしている定番の本を読み漁りました。関連本・文献数は300本以上は読んだと思います。(もちろん本だけではなく、記事や動画、Podcastなどのインプットも含めてですが)
今回は、そんな方に向けて、プロダクトマネジメント(プロダクトマネージャー/PdM・PM)やプロダクト開発に関連するおすすめ本を紹介していきます!紹介する書籍数が多いため、「プロダクトマネジメントの定番本」「開発技術」「マーケティング・UX」「ビジネス全般」の4テーマに分けています。ぜひ、気になったものがあれば読んでみてください。(一部のコンテンツにプロモーションが含まれています)
▼関連記事
・「戦略」を学びたい人におすすめ本ランキング!良書・名著を厳選
・プロジェクトマネジメントのおすすめ本ランキング
プロダクトマネジメントの定番本
まずはプロダクトマネジメントの定番本をご紹介します!こちらは言わずとしれた定番の本ばかりなので、既に読んだことがあるかもしれません。自分も上司から読むことを強く薦められた本で、実際に良かったものを抜粋しています。
これら本で記載されているスキルや考え方は、現場で戦っているプロダクトマネージャーはほとんどが熟知されていることなので、必読と言っても過言ではないです。
世界で通用するプロダクトの創り方 ― “優れたプロダクト”はどのようにして成功したか?
手前味噌で恐縮ですがまず私が2025年5月に出版させていただいた「世界で通用するプロダクトの創り方 ― “優れたプロダクト”はどのようにして成功したか?」を紹介させてください!
本書は、「Notion」「Zoom」「Airbnb」「Duolingo」など世界で成功した15のプロダクトを徹底的に解剖し、抽象化した6つの成功原則に落とし込んだ書籍です。グローバルに通用するサービスを生み出すための具体的な戦略や創業時の舞台裏エピソードが豊富で、読み物としても面白いと思います。数多くの事例とデータに裏打ちされた成功法則を学ぶことで、プロダクトマネージャーとして自社プロダクトを「世界標準」のレベルへ押し上げるためのヒントを得られる一冊です!
▼書籍概要
| 書籍名 | 世界で通用するプロダクトの創り方 ― “優れたプロダクト”はどのようにして成功したか? |
| 発売日 | 2025/5/10 |
| 著者 | 若狭 烈 |
| 本の概要 | 世界で飛躍した15プロダクトの事例を通じ、6つの共通成功原則を解き明かす実践ガイド |
| どんな人におすすめか | ・グローバル展開やエコシステム設計を学びたいスタートアップ経営者 ・プロダクトの成功法則やUX設計、コミュニティ戦略などを学びたいプロダクトマネージャー・UXデザイナー ・ネットワーク効果の実装や招待制から大衆への拡散手法を知りたいマーケター/グロース担当 |
| ページ数 | 154ページ |
| 中身(目次) | 序章 世界で通用するプロダクトとは何か? 第1章 Notion:ユーザーを虜にしたオールインワン・ワークスペース 第2章 Zoom:シンプルさと信頼性で勝ち取ったビデオ会議の世界標準 第3章 Airbnb:「信頼」を設計した宿泊プラットフォームの挑戦 第4章 Shopify:個人商店を支えるグローバルECエコシステム 第5章 Spotify:音楽業界を変えたパーソナライズ戦略 第6章 Duolingo:ゲーム感覚で習慣化させた世界最大の語学学習プラットフォーム 第7章 Netflix:DVD宅配からストリーミング革命へ、自ら変革し続ける巨人 第8章 Slack:ゲームの副産物が生んだ業務通信の新常識 第9章 Canva:非デザイナーのための創造ツール革命 第10章 Discord:ゲーマー発、万人に広がるコミュニティ空間 第11章 Uber:移動の常識を塗り替えたライドシェア革命 第12章 Pinterest:ビジュアルでユーザーの心を掴んだ発見プラットフォーム 第13章 Stripe:開発者ファーストで築いた決済プラットフォーム革命 第14章 Miro:リモート時代のホワイトボードコラボレーション 第15章 Figma:ブラウザ上で実現したデザイン協働革命 終章 15社に学ぶ世界で成功するプロダクトの原則 参考文献 |
| 読んだ人のクチコミ | ・”zoomの“シンプルさ”とNetflixの“自ら変革し続ける姿勢”など、多彩なケースを横断して学べる。 ・Duolingoのゲーミフィケーション、ShopifyのECエコシステム構築…各章ごとに“成功の仕組み”が明快に整理されています。 ・Figmaの“協働革命”やSlackの“副産物から生まれたイノベーション”など、舞台裏エピソードが面白かったです。 ・ユーザー課題への徹底フォーカス、UXの“クリック3回以内”設計、そして継続的なイノベーションなど、プロダクト戦略の全体像がクリアになりました。 |
INSPIRED 熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント
本書「INSPIRED 熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント」はシリコンバレーで行われているプロダクトマネジメントの手法や事例を体系的にまとめてくれた本です。製品開発手法、ゴール設定、メンバー構成と役割について、プロダクトロードマップ、プロトタイプでの検証テクニック、など盛りだくさんな内容で、入門者は一番最初にこの本を読んで欲しいぐらいおすすめです。自分のバイブル本になっています。
ちなみに、何度も読み返したいので、自分は紙と書籍の両方を持っています。もっと言うと、こちらは2ND EDITIONなのですが、1ST EDITIONをプロダクトマネジメントを目指している時にKindleで読みました。(現在は絶版ですが)自分は1STのほうが役に立つことが書いてある印象だったので、もしKindleなどで知人から借りられるなら、ぜひ読んでおきたい一冊です。
▼書籍概要
| 書籍名 | INSPIRED 熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント |
| 発売日 | 2019/11/1 |
| 著者 | マーティ・ケーガン, 佐藤真治, 関満徳, 神月謙一 (翻訳) |
| 本の概要 | シリコンバレーで行われているプロダクトマネジメントの手法や事例を体系的にインプットできる。 |
| どんな人におすすめか | プロダクトマネージャー、エンジニア、デザイナーなどのプロダクト開発に関わる人、これからPdM・PMとして活躍したい人 |
| おすすめポイント | プロダクト開発手法、ゴール設定、メンバー構成と役割について、プロダクトロードマップ、プロトタイプでの検証テクニック、などプロダクトマネジメントに必要な知識が網羅的に書かれています。 |
| 中身(目次) | PART 1 一流IT企業から学んだこと PART 2 適切な人材 ・製品開発チーム ・スケールアップにおける人 PART 3 適切な製品 ・製品開発ロードマップ ・製品ビジョン ・製品の目標 ・スケールアップにおける製品 PART 4 適切なプロセス ・製品の発見 ・発見のフレーミングテクニック ・発見のプランニングテクニック ・発見のアイディエーションテクニック ・発見のプロトタイピングテクニック ・発見のテストテクニック ・トランスフォーメーションのテクニック ・スケールアップにおけるプロセス PART 5 適切な文化 |
| 読んだ人のクチコミ | ・プロダクトマネージャーのバイブル本です ・優れた製品を生み出したい人にまずおすすめしたい一冊 ・翻訳が少し冗長だが、手元に辞書として置いておきたいです ・プロダクトマネジメントを網羅的に入門したい最適 |
プロダクトマネジメントのすべて
こちらの本も多岐に渡るプロダクトマネジメントの範囲を体系的・網羅的に解説してくれている良書です。著者の及川卓也さんはマイクロソフトやグーグルでプロダクトマネジメントをしてきた百戦錬磨のPdMです。自分が見習いPdMのときにこの本が世の中にあって欲しかった!未学習者がプロダクトマネジメントをより広く学ぶために有益な書籍だと思います。
『プロダクトマネジメントのすべて』という名前の通りカバー範囲がとても広く、プロダクト開発手法はもちろん、マーケティング、組織運営、UXなど、幅広く教科書的な説明をしてくれています。ツール紹介も豊富で、たとえばユーザーストーリーマッピングや、バリュー・プロポジション・キャンバスなど、実務で使えるフレームワークも多数掲載されています。
こちら著者の曽根原さんが登壇されているYoutube動画も勉強になるので貼り付けておきます!
※本書は「チーム開発のおすすめ本・書籍ランキング〜定番、入門書、初心者向けなど〜」でも紹介しています^^
▼書籍概要
| 書籍名 | プロダクトマネジメントのすべて |
| 発売日 | 2021/3/3 |
| 著者 | 及川 卓也, 曽根原 春樹, 小城 久美子 |
| 本の概要 | 日本とシリコンバレーのあらゆる知見を詰め込み書き上げた、プロダクトマネジメントの決定版。プロダクト開発手法はもちろん、マーケティング、組織運営、UXなど、幅広く教科書的な説明しています。新サービス立ち上げ・開発、既存事業のDX、スタートアップなど幅広い分野で応用できる知識やフレームワークをぜひ習得しましょう! |
| どんな人におすすめか | プロダクトマネージャー、エンジニア、デザイナーなどのプロダクト開発に関わる人、これからPdM・PMとして活躍したい人、DXをしていきたい人 |
| おすすめポイント | 名前の通りプロダクトマネジメントのすべてが書かれています。プロダクト開発やプロダクトマネジメントに関わる手法、ツール、考え方などが体系的にまとまっている良書です。 |
| 中身(目次) | PartⅠ プロダクトの成功 PartⅡ プロダクトを育てる PartⅢ ステークホルダーをまとめ、プロダクトチームを率いる PartⅣ プロダクトの置かれた状況を理解する PartⅤ プロダクトマネージャーと組織の成長 PartⅥ プロダクトマネージャーに必要な基礎知識 |
| 読んだ人のクチコミ | ・書籍名がすべてを物語っている!プロダクトマネジメントのすべてを網羅的に解説してくれています! ・PdMになりたての後輩をはじめ、エンジニアやデザイナー含めてチームメンバー全員の課題図書にしています ・深く狭くというよりは、浅く広くという網羅性重視の構成なので、実務経験があってある程度インプットもしている人にとっては少々物足りないかもしれません。ただ、それでも広範囲に渡って解説をしているので、辞書的に使えそうです。 ・1冊おいて、ときどき読み返したい類の本です。 |
プロダクトマネージャーになりたい人のための本
「プロダクトマネージャーになりたい人のための本」は、プロダクトマネジメントに強みを持つ転職エージェントで1,200名以上の面談実績を誇るPMキャリアアドバイザーの著者陣と、PM界隈の著名人である及川 卓也氏らが書いた、その名のとおりプロダクトマネージャーになりたい人のための本です。
未経験でこれからプロダクトマネージャーになりたい方はもちろん、現役PMのキャリアアップに関する情報も掲載されており、幅広くPM/PdMという職種について興味がある人におすすめです!
▼書籍概要
| 書籍名 | プロダクトマネージャーになりたい人のための本 |
| 発売日 | 2023/6/14 |
| 著者 | 松永 拓也、山本 航、武田 直人、及川 卓也 (読み手) |
| 本の概要 | プロダクトマネジメントに強みを持つ転職エージェントで1,200名以上の面談実績を誇るPMキャリアアドバイザーの著者陣と、PM界隈の著名人である及川 卓也氏らが書いた、その名のとおりプロダクトマネージャーになりたい人のための本 |
| どんな人におすすめか | ・プロダクトマネージャーになりたい人 ・プロダクトマネージャーの必要スキル、キャリア、転職活動について理解したい人 ・現役プロダクトマネージャー、見習いプロダクトマネージャーの人 |
| おすすめポイント | エンジニア、事業企画、CS・マーケター、デザイナーなどの別職種の方がどのようにプロダクトマネージャー(PM/PdM)を目指すのか?転職支援をした経験から客観的な情報も交えつつご紹介します。また現役PMにとっても役に立つポイントも紹介されており、幅広くプロダクトマネージャーに興味・関心がある方に役立つ内容となっています。 |
| 中身(目次) | 序章 なぜいま、プロダクトマネージャーが必要か 第1章 プロダクトマネージャーの業務と能力を理解する 第2章 プロダクトマネージャーのキャリア形成にむけての基礎知識 第3章 プロダクトマネージャーの転職活動の進め方 第4章 一人のプロダクトマネージャーとして立ち上がる 第5章 プロダクトマネージャーとしてさらに高みを目指す |
| 読んだ人のクチコミ | ・プロダクトマネージャーという職種について解像度が上がりました ・PMとして転職したい自分にとってとても有益で参考になる書籍でした。これから本書の内容を活かして転職活動を頑張っていきたいです ・現役PMです。これからどのようにスキルを伸ばし、キャリアアップしていくかを迷っていたので本書を参考にして少し道がひらけた気がします! |
プロダクトマネージャーのしごと
次に紹介するプロダクトマネジメント定番本は『プロダクトマネージャーのしごと 第2版 ―1日目から使える実践ガイド』です。数年以上のPM/PdMの経験がある私としては、現在日本語で出ているPdM関連の書籍で最も良質な内容だと思います。(ただ、ここまでに紹介した本は体系的で網羅性が高いタイプの本なので先に紹介しました。実践的なプロダクトマネジメントを重視するなら本書がNo1です)
原著名は「Product Management in Practice」なので、その名の通り「実際のプロダクトマネジメント」が書かれています。プロダクトマネジメントの日々の業務とそれを行う方法の紹介はもちろん、プロダクトマネジメントで重要な4つのスキル(コミュニケーション、組織力、リサーチ、実行)を習得する方法を解説したり、まさに実践ガイドです。
▼書籍概要
| 書籍名 | プロダクトマネージャーのしごと 第2版 ―1日目から使える実践ガイド |
| 発売日 | 2023/9/5 |
| 著者 | Matt LeMay、永瀬 美穂 (翻訳)、吉羽 龍太郎 (翻訳)、原田 騎郎 (翻訳)、高橋 一貴 (翻訳) |
| 本の概要 | プロダクトマネジメントの日々の業務とそれを行う方法の紹介はもちろん、プロダクトマネジメントで重要な4つのスキル(コミュニケーション、組織力、リサーチ、実行)を習得する方法を解説しています。 |
| どんな人におすすめか | ・プロダクトマネージャーの実践的なスキルを身に着けたい人 ・現役プロダクトマネージャー、見習いプロダクトマネージャーの人 ・教科書的ではなくPM/PdMの実態、実践的なスキル、業務内容について学びたい人 |
| おすすめポイント | とにかく実践的な内容です!よくある教科書的な内容やフレームワークの説明をするのではなく、実際の業務を踏まえています。入門書で基礎や概念、フレームワークを抑えた人や、すでにプロダクトマネージャーとして働いている方の飛躍の一冊としておすすめです。 |
| 中身(目次) | 1章 プロダクトマネジメントの実践 2章 プロダクトマネジメントのCOREスキル 3章 好奇心をあらわにする 4章 過剰コミュニケーションの技術 5章 シニアステークホルダーと働く(ポーカーゲームをする) 6章 ユーザーに話しかける(あるいは「ポーカーって何?」) 7章 「ベストプラクティス」のワーストなところ 8章 アジャイルについての素晴らしくも残念な真実 9章 ドキュメントは無限に時間を浪費する(そう、ロードマップもドキュメント) 10章 ビジョン、ミッション、達成目標、戦略を始めてとしたイケてる言葉たち 11章 「データ、舵を取れ!」 12章 優先順位づけ:すべてのよりどころ 13章 おうちでやってみよう:リモートワークの試練と困難 14章 プロダクトマネージャーのなかのマネージャー(プロダクトリーダーシップ編) 15章 良いときと悪いとき 16章 どんなことでも 付録A プロダクトマネジメント実践のための読書リスト 付録B 本書で引用した記事、動画、ニュースレター、ブログ記事 |
| 読んだ人のクチコミ | ・プロダクトマネージャーとして実際の業務がイメージできました ・PdMの日々の業務と実践を解決した良書です。入門者やこれからPdMを目指したい人にもおすすめの一冊です ・とにかく実践的な内容でおすすめ!教科書的でフレームワークばかり紹介するPM本に飽きている人は絶対満足できると思います |
プロダクトマネジメント ―ビルドトラップを避け顧客に価値を届ける
本書『プロダクトマネジメント ―ビルドトラップを避け顧客に価値を届ける』は2020年10月発売と比較的新しい本で、タイトルのとおりプロダクトマネジメントについて学ぶことができる良書です。本書では特に「ビルドトラップ」という、アウトカムではなくアウトプットで良し悪しを測定して行き詰まっている状態や、生み出した価値ではなく機能開発とリリースに集中している状態について、その兆候や対策について説明されています。「【書評・要約】プロダクトマネジメント ―ビルドトラップを避け顧客に価値を届ける」でも詳細を取り上げています!
このビルドトラップという考え方は目からウロコで、どうしても目に見えるアウトプットで一喜一憂しがちなので、いかにアウトカム重視のチームにするか?など大変参考になります。
本書はヤフーニュースのプロダクトオーナーが登壇したウェビナーでも一部紹介されていました。(この動画はPdMとしてどうスキルを身に着けてステップを踏んでいくかがわかるのでオススメです♪)
▼書籍概要
| 書籍名 | プロダクトマネジメント ―ビルドトラップを避け顧客に価値を届ける |
| 発売日 | 2020/10/26 |
| 著者 | Melissa Perri、吉羽 龍太郎(翻訳) |
| 本の概要 | 顧客に価値を届けるプロダクトを作り出すプロダクトマネジメントについて学ぶ本です。アウトプットを重視する企業が陥りがちなビルドトラップについて、その原因と防ぐ方法について詳しく解説があります。 |
| どんな人におすすめか | リリースすることを目標・ゴールに置くことに違和感を感じているプロダクトマネージャー(PdM)。成果物ではなく成果を出すためにどうすればよいのか? |
| おすすめポイント | 「作るもの」ではなく「解決する課題」にフォーカスするプロダクトマネジメントがなぜ必要なのか?どうすればビルドトラップから抜け出せるのか?具体的な戦略・方針の作成方法がわかります。 |
| 中身(目次) | 第I部 ビルドトラップ 1章 価値交換システム 2章 価値交換システムの制約 3章 プロジェクト / プロダクト / サービス 4章 プロダクト主導組織 5章 私たちが知っていること、知らないこと 第II部 プロダクトマネージャーの役割 6章 悪いプロダクトマネージャーの典型 7章 優れたプロダクトマネージャー 8章 プロダクトマネージャーのキャリアパス 9章 チームを構成する 第III部 戦略 10章 戦略とは何か? 11章 戦略のギャップ 12章 良い戦略フレームワークを作る 13章 企業レベルでのビジョンと戦略的意図 14章 プロダクトビジョンとポートフォリオ 第IV部 プロダクトマネジメントプロセス 15章 プロダクトのカタ 16章 方向性の理解と成功指標の設定 17章 問題の探索 18章 ソリューションの探索 19章 ソリューションの構築と最適化 第V部 プロダクト主導組織 20章 アウトカムに着目したコミュニケーション 21章 報酬とインセンティブ 22章 安全と学習 23章 予算編成 24章 顧客中心主義 25章 マーケットリー:プロダクト主導企業 おわりに:ビルドトラップから抜け出してプロダクト主導になる 付録A 企業がプロダクト主導かどうかを判断する6つの質問 |
| 読んだ人のクチコミ | ・PdMだけではなく、CxO、エンジニアリングマネージャー、UXD、プロジェクトマネージャーなどプロダクト開発に関わる人みんなに読んでほしい一冊! ・ビルドトラップという陥りがちな落とし穴がよくわかります ・具体的にどのように目標をたて、方針を作るのかがよくわかります。実務で使える本です。 |
ジョブ理論
こちらの「ジョブ理論」もプロダクトマネジメントに携わる方は必読書です。あの「イノベーションのジレンマ」を書いたクレイトン・クリステンセン教授が執筆した本で、ジョブ理論の説明をしたミルクシェイクの事例はあまりにも有名です。顧客は”片付けたいジョブ”を持っていて、そのジョブを解決するために商品を“雇用”しているという考え方は、プロダクトマネジメントにおいて非常に重要な考え方です。
※本書は「イノベーションのおすすめ本・書籍ランキング〜定番、名著、入門書など〜」でも紹介しています^^
▼書籍概要
| 書籍名 | ジョブ理論 |
| 発売日 | 2017/8/1 |
| 著者 | クレイトン M クリステンセン、タディ ホール、カレン ディロン、デイビッド S ダンカン、依田 光江 (翻訳) |
| 本の概要 | 人がモノを買うメカニズムを徹底解明!消費者が商品を買う際には目的(ジョブ)があり、そのジョブを解決するために商品を購入しているという考え方 |
| どんな人におすすめか | 顧客のニーズ・買う理由を紐解きたいPdM・PM、プロダクトマネジメントに関わる人、これからプロダクトマネージャーになりたい人 |
| おすすめポイント | 顧客の購買メカニズムを詳細に分析し、どのようにイノベーションを起こしていくのか?さらにそれをどう事業・プロダクトに落とし込んでいくべきか?が事例とセットで理解できる |
| 中身(目次) | 序章 この本を「雇用」する理由 第1章 ミルクシェイクのジレンマ 第2章 プロダクトではなく、プログレス 第3章 埋もれているジョブ 第4章 ジョブ・ハンティング 第5章 顧客が言わないことを聞き取る 第6章 レジュメを書く 第7章 ジョブ中心の統合 第8章 ジョブから目を離さない 第9章 ジョブを中心とした組織 第10章 ジョブ理論のこれから |
| 読んだ人のクチコミ | ・プロダクトマネージャーだけでなくビジネスマン全員が一読すべきです ・派手さは無いですが、本質的な顧客購入の理由が理論化されています ・正しいジョブを理解することがいかに大切かが分かります ・分厚い本で読むのに時間がかかるが、それを掛ける価値がある一冊 |
リーン・スタートアップ
次にご紹介するプロダクトマネージャーの定番本は、『リーン・スタートアップ』です。こちらは、ぼくの前職の師匠とも呼べる人が「リーン・スタートアップのアプローチで新規事業を探ってます」と何度も話していたことで知りました。もともとはシリコンバレーで採用されていた手法ですが、今では多くのスタートアップやテックベンチャーが採用している製品・サービス開発手法として、とても知名度があります。検証による学びを得ていく開発スタイルは、いまでは当たり前となっています。まだ読んでない方はぜひ一度読んでみてください。「新規事業立ち上げのおすすめ本ランキング!現役コンサルタントが厳選」や「スタートアップのおすすめ本・書籍ランキング〜定番、入門書、初心者向けなど〜」でも紹介しています。
※本書は「起業のおすすめ本ランキング〜定番、ひとり起業、女性の起業〜」でも紹介している良書です^^
▼書籍概要
| 書籍名 | リーン・スタートアップ |
| 発売日 | 2012/4/12 |
| 著者 | エリック・リース、伊藤 穣一(MITメディアラボ所長)、井口 耕二 (翻訳) |
| 本の概要 | 世界を変えるスタートアップが数多く生み出されているシリコンバレーで採用されているプロダクト・事業開発をしていくための方法論である「リーンスタートアップ」について豊富な事例とともに解説されています。 |
| どんな人におすすめか | これから起業しようとしている人、プロダクト立ち上げ、新規事業立ち上げなどサービス開発に携わっている(携わりたい)人、PdMやPMを目指す人 |
| おすすめポイント | 先が見えない不確実な時代に、誰も欲しがらない製品を作ってしまうリスクをどのようにへらすか?ムダをなくし、顧客やユーザーが求める製品・サービスを、どうすれば早く生み出し続けることができるのか?実践で使うための方法論が事例と合わせて紹介されています。 |
| 中身(目次) | 第1部 ビジョン(スタート 定義 学び ほか) 第2部 舵取り(始動 構築・検証 計測 ほか) 第3部 スピードアップ(バッチサイズ 成長 順応 ほか) |
| 読んだ人のクチコミ | ・言わずとしれた名著。プロダクトマネジメントに関わる人は一読すべき。 ・実例が豊富でリーンスタートアップとは何かがイメージがしやすい ・スタートアップに限らず新規事業、サービス開発などで応用できる本です |
Running Lean ―実践リーンスタートアップ
こちらは先程のリーン・スタートアップを実践するときに大変参考になる良書『Running Lean ―実践リーンスタートアップ』です。どのように、リーン・スタートアップを実践していけばいいのか?具体的な方法論や進め方を学ぶことができます。リーンキャンバスなど、自分も実際の現場で活用してきたフレームワークの紹介などもあり、スタートアップや新規事業においても役立つ内容が豊富です。
▼書籍概要
| 書籍名 | Running Lean ―実践リーンスタートアップ |
| 発売日 | 2012/12/21 |
| 著者 | アッシュ・マウリャ、渡辺 千賀、エリック・リース、角 征典 (翻訳) |
| 本の概要 | リーン・スタートアップを実践するときに具体的にどうすれば良いのか、リーンキャンバスやユーザーインタビューの手法を用いて解説してくれている本です。いわゆるMVPを構築する方法や、構築・計測・学習のループを高速に回す方法、などタイトル通り実践的な内容になっております。 |
| どんな人におすすめか | リーン・スタートアップの概念は理解したけど具体的に実践するイメージが沸かない人。顧客インタビューで具体的にどのように進行・質問すればよいか知りたい人。新規事業を立ち上げたい人、プロダクトマネージャー、PM、UXデザイナー |
| おすすめポイント | 今では当たり前にやるべきと言われているユーザーインタビュー(N1インタビュー)を具体的にどう設計し、どう質問すれば良いのか?など実践的なプロダクト開発ノウハウがわかります。 |
| 中身(目次) | 第1部 ロードマップ(メタ原則 Running Leanの実例) 第2部 プランAを文書化する(リーンキャンバスの作成) 第3部 プランで最もリスクの高い部分を見つける(ビジネスモデルの優先順位、実験の準備) 第4部 プランを体系的にテストする(顧客インタビューの準備、課題インタビュー ほか) |
| 読んだ人のクチコミ | ・起業を考えている人、プロダクト立ち上げをしたい人、企画でPOC段階からどうやるか知りたい人など、プロダクト開発・新規立ち上げに関わる人にオススメしたい書籍です ・リーン・スタートアップの実践方法や、実践して成功した人の事例が分かります ・リーンキャンバスの使い方を学べるだけでもとても有意義でした |
リーン顧客開発
次もリーン・スタートアップ関連本です。『リーン顧客開発』は売れないリスクを最小化するためのインタビューなどを実践するための手引書です。リーン・スタートアップを実践したい人は必読書ですが、どちらかというと新規プロダクトかつ、SaaSなどのtoB向けプロダクトに向いている気がします。
▼書籍概要
| 書籍名 | リーン顧客開発 |
| 発売日 | 2015/4/25 |
| 著者 | シンディ・アルバレス、堤 孝志、飯野 将人、エリック・リース、児島 修 (翻訳) |
| 本の概要 | 「作ったけど売れない」というよくある起業やプロダクト開発の罠に陥らないためにはきちんと顧客の課題、解決策をセットで考えて、それを明らかにしていくことが必要不可欠です。本書ではリーン顧客開発と称して、売れないリスクを極小化するための方法論を解説します。 |
| どんな人におすすめか | リーン・スタートアップの概念は理解したけど具体的に実践するイメージが沸かない人。ユーザーインタビューの技術・手法を知りたい起業家、プロダクトマネージャー、UXデザイナー、スタートアップ社員、PdMやPMを目指す人 |
| おすすめポイント | 仮説と検証を繰り返すことで顧客を理解し、適切なセグメントに向けた製品を迅速に開発する手法について詳しく知ることができます。 |
| 中身(目次) | 1章 なぜ顧客開発が必要なのか 2章 どこから始めるべきか? 3章 誰と話をすべきか? 4章 何を学習すべきか? 5章 オフィスから飛び出せ 6章 検証済みの仮説はどのように見えるのか? 7章 実用最小限の製品をどのように開発すべきか? 8章 既存顧客がいる場合の顧客開発 9章 継続的な顧客開発 付録 効果的な質問 |
| 読んだ人のクチコミ | ・ターゲット顧客のプロフィールをマッピングする方法から、顧客の行動背景や課題を明確にするインタビューのコツまで顧客開発の手法をとことん学べます ・プロダクトマネジメントやUXデザインに関わる人は一度は読んでおきたい本です! ・ユーザーインタビューの手法や技法についての説明が多いです! |
ゼロから始めるプロダクトマネジメント
まだ未経験で、これからプロダクトマネージャーになりたいと思っている方には、入門書として『ゼロから始めるプロダクトマネジメント』を紹介します!プロダクトマネージャーの仕事を物語形式で解説してくれます。ある程度経験した方は不要かと思いますが、取っ掛かりとして優れたおすすめ本だと思います。
余談ですが本書の主人公のたかし君、中学生2年生なのですがこのペースでプロダクト開発の経験を積んでいったら、大学生や20代の時にはとんでもないレベルの起業家になりそうな成長スピード&実績です(笑)
▼書籍概要
| 書籍名 | ゼロから始めるプロダクトマネジメント |
| 発売日 | 2020/8/26 |
| 著者 | 丹野瑞紀 |
| 本の概要 | ソフトウェアプロダクトの企画~開発~リリース~改善までの課題や乗り越える方法を、中学2年生の主人公がアプリ開発していくという物語を通じて説明! |
| どんな人におすすめか | ソフトウェアプロダクトのマネジメントを学びたい人、見習いPdM、PdMを目指している人、サービス開発について知りたいセールス、CS、企画職の人。 |
| おすすめポイント | ストーリー形式でプロダクトマネジメントを入門できます。ユーザー体験を作る側面だけでなく、事業を成立させるためのマネタイズ面まで解説してくれる書籍です。同じチームや未経験メンバーの育成目的で読んでもらうのもアリ。 |
| 中身(目次) | 第1章 みんなが困っていることはなんだろう ~ユーザーが抱える問題の仮説をたてる 第2章 アプリを完成させよう ~最小限の機能セットからはじめる 第3章 アプリはどう使われている? ~ユーザーの利用状況を把握する 第4章 使い続けてもらう工夫をしよう ~エンゲージメントを獲得する 第5章 もっと多くの人に知ってもらおう ~プロダクトの認知を獲得する 第6章 儲かるしくみを作ろう ~エコノミクスを成立させる 第7章 プロダクトマネジメントを始めよう! |
| 読んだ人のクチコミ | ・ストーリー形式なのでプロダクトやサービス開発の流れがわかりやすいです ・AARRRモデル、コホート分析、バリュープロポジション、ストーリーボードなどシニアPMが使うキーワードもしっかり解説されてます! ・経験者には物足りない内容ですが未経験やこれからPdM・PMを目指したい人にはぜひ読んでもらい一冊 |
プロダクトマネジメントの教科書 PMの仕事を極める ― スキル、フレームワーク、プラクティス
プロダクトマネージャーとしてのキャリアについて学びたい人向けの「プロダクトマネジメントの教科書 PMの仕事を極める ― スキル、フレームワーク、プラクティス」です。Cracking the PM Careerの翻訳書で、原著はAsanaのPMが執筆したとのこと。
▼書籍概要
| 書籍名 | プロダクトマネジメントの教科書 PMの仕事を極める ― スキル、フレームワーク、プラクティス |
| 対象レベル | 初心者〜中級者 |
| ひとこと説明 | Cracking the PM Careerの翻訳書!プロダクトマネージャーになりたい人、現役PDM・PMの方におすすめの一冊 |
| 著者 | Jackie Bavaro (著), Gayle Laakmann McDowell (著), 竹村 光 (翻訳) |
| 発売日 | 2024/1/22 |
| ページ数 | 496ページ |
| 出版社 | マイナビ出版 |
| 中身(目次) | A まえがき B プロダクトマネージャーの役割 C プロダクトスキル 4章 ユーザーインサイト 5章 データインサイト 6章 分析的問題解決力 7章 プロダクトデザインスキル 8章 技術的なスキル 9章 プロダクト仕様書の作成 D 実行スキル 10章 プロジェクトマネジメントスキル 11章 スコープ定義とインクリメンタル開発 12章 プロダクトローンチ 13章 物事を成し遂げる力 E 戦略的スキル 14章 プロダクト戦略の概要 15章 ビジョン 16章 戦略フレームワーク 17章 ロードマップと優先順位付け 18章 チームの目標 F ピープルマネジメントスキル 19章 パーソナルマインドセット 20章 コラボレーション 21章 権威に頼らない影響力 22章 コミュニケーション 23章 モチベーションとインスピレーション 24章 チームの目標 25章 メンタリング 26章 他部門とのコラボレーション G リーダーシップスキル 27章 ピープルマネージャーになる 28章 新しいリーダーシップスキル 29章 コーチングと能力開発 30章 チームを作る 31章 組織を設計する H キャリア 32章 キャリアラダー 33章 キャリアプラン 34章 キャリアアップのためのスキル 35章 さらに学びたい人へ 36章 PMを越えて I プロダクトリーダーQ&A J 追加情報 48章 PMのタイプ 49章 PMの仕事に就くために 50章 内向的な人のためのネットワーキング 51章 自律性と評価のパラドックス 52章 オファー交渉のための10のルール K 付録 53章 役立つキーフレーズ 54章 略語集 |
| 読んだ人のクチコミ | Cracking the PM Careerの翻訳書です。プロダクトマネジメントに関して必要なスキルやフレームワークが掲載されている他、世界中で活躍するプロダクトリーダーのインタビューが掲載れており非常に有益です。 |
購入はこちら
ソフトウェア・ファースト
こちらの『ソフトウェア・ファースト』はプロダクトマネジメントを直接的な題材にしているわけではありませんが、前述の『プロダクトマネジメントのすべて』と同じく及川氏による著書です。現代のプロダクト企画や、アジャイル開発手法の本質、狩野モデルなどの解説や、ネットフリックスとブロックバスターの競争の事例など、実際の事例も踏まえて解説してくれています。プロダクトマネージャーは様々なステークホルダーと対話が必要だったりするので、こういった事例や知識をインプットしておくことは非常に大切です。ぜひご一読ください。
▼書籍概要
| 書籍名 | ソフトウェア・ファースト |
| 発売日 | 2019/10/10 |
| 著者 | 及川 卓也 |
| 本の概要 | あらゆるビジネスがソフトウェア中心に刷新されている現代の世の中において、どのようにデジタルシフト・DX・製品開発をしていけばよいのか?手法や事例を幅広く解説してくれています。 |
| どんな人におすすめか | プロダクト開発をより現代に沿う形にアップデートしたい開発者、マネージャー、経営者。 |
| おすすめポイント | 概念的な話に終始せず、ソフトウェア・IT産業の歴史的背景から、なぜソフトウェアファーストが重要なのか、どうすればそのような組織がつくれるのか、などのテーマを豊富な事例とセットで解説してくれます。事例だけでも読む価値があります。 |
| 中身(目次) | 1章:ソフトウェア・ファースト 2章: IT・ネットの“20年戦争”に負けた日本の課題と光明 3章:ソフトウェア・ファーストの実践に必要な変革 4章:これからの「強い開発組織」を考える 5章:ソフトウェア・ファーストなキャリアを築くには |
| 読んだ人のクチコミ | ・非エンジニアがエンジニアを理解するために読むもよし。エンジニアが非エンジニアを理解するために読むもよし。 ・事例だけでも読む価値があります ・日本のソフトウェア、IT化の課題が浮き彫りになっています |
開発・技術
プロダクトマネージャーといえば、技術的な知識・システム面のスキルも必要不可欠な職種です。もちろん、どの程度の技術スキルが必要になるかは会社や部署によりけりですが、それでも最低限の部分はカバーしておく必要があります。そのためのおすすめ本を紹介いたします。
具体的にどういった技術スキルが必要か?などは『プロダクトマネージャーに必要な技術的な知識・スキルについて』の記事でも紹介していますので、合わせてご確認ください!また、プロダクトを作る上で必須となる要件定義スキルは「要件定義・上流工程のおすすめ本ランキング」でも紹介しています。
プロになるためのweb技術入門
まずは基本的なシステム開発、システム構成について理解をする必要があります。『「プロになるためのWeb技術入門」 ――なぜ、あなたはWebシステムを開発できないのか』はサブタイトルが開発者向けですが、実際にはディレクターやプロダクトマネージャーも確実に知っておくべき範囲を解説してくれています。
通信技術とソフトウェア開発技術の両面から、Webシステムのしくみをひとつひとつ確実に解説してくれており、ITに携わる方の基礎レベルが網羅されています。エンジニアと議論、協働していくためにもぜひ本書レベルの知識は習得してくださいね♪
▼書籍概要
| 書籍名 | 「プロになるためのWeb技術入門」 ――なぜ、あなたはWebシステムを開発できないのか |
| 発売日 | 2010/4/10 |
| 著者 | 小森 裕介 |
| 本の概要 | Webアプリケーションの開発方法を、インターネットの仕組みという根本的な部分から豊富な図解を用いてわかりやすく解説します。HTTP通信、サーバー、データベース、セキュリティの知識などもカバー。仕事で実践するための基盤となる知識を身につけるためにとても有益。 |
| どんな人におすすめか | エンジニアの話している内容が理解できない企画・PdM・PjM、デザイナーの人、webシステムの構造を基礎的な部分から理解したい人、若手エンジニア、WEBアプリケーション開発のPMをしているが、技術がイマイチわかってない人 |
| おすすめポイント | webアプリケーションの開発手法を原理原則の深い部分から解説!図解が豊富なので初心者でも分かりやすいです。 |
| 中身(目次) | LESSON 0:プロローグ LESSON 1:「Webアプリケーション」とは何か LESSON 2:Webはどのように発展したか LESSON 3:HTTPを知る LESSON 4:CGIからWebアプリケーションへ LESSON 5:Webアプリケーションの構成要素 LESSON 6:Webアプリケーションを効率よく開発するための仕組み LESSON 7:セキュリティを確保するための仕組み LESSON 8:おわりに LESSON 9:付録 |
| 読んだ人のクチコミ | ・エンジニア職ではないですが、web技術の基礎が勉強になりました ・本書が無かったらエンジニアとシステム開発・ディレクションをするときの会話にもっと苦戦していた気がします(笑) ・少し前の本ですが侮るなかれ!webシステム、アプリケーションの根本的な部分を説明してくれるので色褪せません。 |
カイゼン・ジャーニー
プロダクトマネジメントする上で必須とも言える開発プロセスについて学べるおすすめ本が『カイゼン・ジャーニー』です。チーム作業だけではなく、個人のタスクマネジメント手法からはじまり、徐々に人数が増えてチーム開発でのタスクの進め方までを幅広く学べます。特に、スクラム開発の用語やフレームワークについてもストーリー形式と解説のパートに分かれており、アジャイルでプロダクト開発をする手法についてとても理解がしやすい良書です。「アジャイル開発・スクラムのおすすめ本ランキング」でも紹介しています^^
また、「仕事の量は、完成のために与えられた時間を満たすまで膨張する」というパーキソンの法則の解説と、どのように対処するか?などの手法まで解説がされており、すぐに実践に使うこともできました。
▼書籍概要
| 書籍名 | カイゼン・ジャーニー |
| 発売日 | 2018/2/7 |
| 著者 | 市谷 聡啓、新井 剛 |
| 本の概要 | アジャイル開発をストーリー形式で学べる良書です。チームマネジメントやプロジェクトリードをするためのツールセットもご紹介しています。 |
| どんな人におすすめか | アジャイル開発でのプロダクト開発手法を知りたい人、チームマネジメントや業務改善をしたい人、プロダクトマネージャーやプロジェクトマネージャー、スクラムマスター |
| おすすめポイント | ストーリー形式と解説形式の2種類で業務改善やチームマネジメント、アジャイルでのプロダクト開発について学ぶことができます。ストーリーでイメージをつけて、解説パートで具体的に理解するという二段階の構成で学習できる点が嬉しいです。 |
| 中身(目次) | ※抜粋※ ●第1部 一人から始める ・第3話 一人で始めるふりかえり ・第4話 一人で始めるタスクの見える化 ●第2部 チームで強くなる ・第9話 一人からチームへ ・第10話 完成の基準をチームで合わせる ・第13話 お互いの期待を明らかにする ・第14話 問題はありませんという問題 ・第15話 チームとプロダクトオーナーの境界 ・第16話 チームとリーダーの境界 ・第17話 チームと新しいメンバーの境界 ●第3部 みんなを巻き込む ・第20話 新しいリーダーと、期待マネジメント ・第23話 デザイナーと、共通の目標に向かう ・第25話 広さと深さで、プロダクトを見立てる ・第26話 チームで共に越える |
| 読んだ人のクチコミ | ・チームでプロダクト開発するときのバイブルになっています ・開発したことが無い人にとてもオススメ!ストーリー形式なのでイメージが掴めます。 ・カイゼンしていくためのヒントを得ることができました |
チーム開発実践入門
こちらの本も開発技術や開発ツールを理解する上で非常におすすめです。『チーム開発実践入門』はGithubなどでのバージョン管理、JIRAやRedmineなどでのチケット管理、継続的インテグレーション、デプロイ、などなど、チームでの開発現場で必要となるツールや知識について幅広く書かれている本です。これらプロジェクトマネジメントに近い要素なので、プロダクトマネージャー(PdM)ではなく、プロジェクトマネージャー(PjM)が行う現場も多いですが、それでも知識として知っている必要があるので、確実にキャッチアップしておきたい内容です。
※本書は「エンジニアのおすすめ本・参考書まとめ〜初心者・中級者向け〜」でも紹介している良書です^^
▼書籍概要
| 書籍名 | チーム開発実践入門 |
| 発売日 | 2014/4/16 |
| 著者 | 池田 尚史、藤倉 和明、井上 史彰 |
| 本の概要 | 複数人でサービス開発をしていくために必要な考え方、ツール、ノウハウを解説しています。Githubなどでのバージョン管理、JIRAやRedmineなどでのチケット管理、継続的インテグレーション、デプロイ、などを幅広く解説した良書です。 |
| どんな人におすすめか | 個人開発は結構経験があるけど複数人でのチーム開発や大規模サービスに関わることになったプロダクトマネージャー、エンジニア、エンジニアリングマネージャーの人。 |
| おすすめポイント | チームでプロダクトやシステムを開発していくために必要な知識、ツール、ノウハウを基礎から学ぶことができます。非エンジニアでも読みやすいですが、内容は濃くてしっかり書かれています。 |
| 中身(目次) | 第1章 チーム開発とは 第2章 チーム開発で起きる問題 第3章 バージョン管理 第4章 チケット管理 第5章 CI(継続的インテグレーション) 第6章 デプロイの自動化(継続的デリバリー) 第7章 リグレッションテスト |
| 読んだ人のクチコミ | ・その名の通りチーム開発を実践的に入門できる本です! ・未経験で入社した企業で先輩社員に必読書として推薦されました。gitって何?CI/CDとは?という状態からスタートしたので、本当に読んでおいてよかったと思います ・プロダクトやシステム開発、ディレクションはじめてでしたが、この本を読んで大まかな流れを掴むことができたので、スムーズに職種転換できました。本当に感謝しています。 |
Webを支える技術
こちらの「Webを支える技術」は言わずとしれたソフトウェア関連の名著でして、もう10年以上前の書籍ですが、基本的な仕組みや構造がメインの内容となっており、今でもあまり廃れていません。RESTなどのWebAPIの設計スタイルや、GET、POST、PUTなどの使い分けなど、エンジニアが普通に知っている内容を解説してくれています。ぜひプロダクトマネージャーもこの辺りはインプットしておきたい内容です。
※本書は「サーバーのおすすめ本・参考書ランキング」でも紹介しています^^
▼書籍概要
| 書籍名 | Webを支える技術 |
| 発売日 | 2010/4/8 |
| 著者 | 山本 陽平 |
| どんな人におすすめか | Webの基礎技術を学びたい人、これからプロダクト開発・開発ディレクションに取り組みたい人、プロダクトマネージャーを目指している人 |
| 中身(目次) | 第1部 Web概論 第1章 Webとは何か 第2章 Webの歴史 第3章 REST ── Webのアーキテクチャスタイル 第2部 URI 第4章 URIの仕様 第5章 URIの設計 第3部 HTTP 第6章 HTTPの基本 第7章 HTTPメソッド 第8章 ステータスコード 第9章 HTTPヘッダ 第4部 ハイパーメディアフォーマット 第10章 HTML 第11章 microformats 第12章 Atom 第13章 Atom Publishing Protocol 第14章 JSON 第5部 Webサービスの設計 第15章 読み取り専用のWebサービスの設計 第16章 書き込み可能なWebサービスの設計 第17章 リソースの設計 |
| 読んだ人のクチコミ | ・RESTとRESTfulの違いやWebAPI設計において基礎的だけど技術的にとても重要なことの理解が深まりました ・Web技術の歴史がまとまっておりIT業界で働く人はマストな知識だと思います ・発売日は少し前の本ですが、本質的な知識なので廃れることは無いです |
スッキリわかるSQL入門 第4版
次の推薦図書はスッキリわかるSQL入門の第4版「スッキリわかるSQL入門 第4版 ドリル256問付き! スッキリわかるシリーズ」です。みなさんはSQLを書けますか?SQLはデータベースからデータを操作する言語で、プロダクトマネージャーが自らデータ抽出する際に非常に頻繁に使用します。SQLが使えるのと使えないのとでは、要件・仕様を策定する精度と速度が圧倒的に変わってきますので、ぜひこちらもマスターしておきたいです。
本書はデータベース(DB)について学べるおすすめ本・参考書24冊やMySQLのおすすめ本・書籍ランキング〜定番、入門書、初心者向けなど〜でも紹介している定番本ですよ♪
▼書籍概要
| 書籍名 | スッキリわかるSQL入門 第4版 ドリル256問付き! スッキリわかるシリーズ |
| 発売日 | 2024/2/5 |
| ページ数 | 528ページ |
| 著者 | 中山 清喬、飯田 理恵子、株式会社フレアリンク (監修) |
| 本の概要 | プログラミング入門書の大人気シリーズ「スッキリわかる入門シリーズ」のSQL版です。ドリルが256問ついており学習→実践→復習を繰り返してスキルを身につけることができます。 |
| どんな人におすすめか | プロダクトマネージャーとしてSQLを使えるようになりたい人、これからSQLを学び始める入門者、見習いPdM |
| おすすめポイント | SQLを勉強していると「なんで動かない?」「このエラーはどうすればいい?」などの壁にぶつかりますが、初学者でも効率よく学んでいくことができます!また第3版でこれまでより実践的で最新の内容に更新されたのでこれから入門する人にピッタリな本です。 |
| 中身(目次) | 第0章 データベースを学ぶにあたって 第Ⅰ部 SQLを始めよう 第1章 はじめてのSQL 第2章 基本文法と4大命令 第3章 操作する行の絞り込み 第4章 検索結果の加工 第II部 SQL を使いこなそう 第5章 式と関数 第6章 集計とグループ化 第7章 副問い合わせ 第8章 複数テーブルの結合 第III部 データベースの知識を深めよう 第9章 トランザクション 第10章 テーブルの作成 第11章 さまざまな支援機能 第IV部 データベースで実現しよう 第12章 データベースの設計 付録 付録A DBMS別互換性簡易リファレンス 付録B エラー解決 虎の巻 付録C 特訓ドリル (SQL・正規化・総合問題) 付録D SQLによるデータ分析 |
| 読んだ人のクチコミ | ・人気シリーズなので信頼感があります ・エラー解決虎の巻きが付属していて、そのおかげで独学でも躓かずに学び通すことができました! ・この本でクエリ入門し、最終的にはエンジニアで社員採用されました。きっかけを作ってくれた本書や著者に大変感謝してます |
購入はこちら
その他にもSQLを学んだ体験談やおすすめ本をまとめております。プロダクトマネージャーでSQLを使いこなせるとかなり強みになるのでぜひ参考にしてください!
【初心者向け】SQLおすすめ本8冊を厳選!(独学で入門するステップ付き)
ビッグデータ分析・活用のためのSQLレシピ
SQLの基本を理解してより高度な分析を現場でしたいPdMにおすすめな本が「ビッグデータ分析・活用のためのSQLレシピ」です。本書は名前の通りSQLをデータ分析に活用したい人のための必読書として人気がある書籍です。
特徴は実務でデータ分析をする上で必要なケースが多数掲載されている点で、例えば「ECサイトの売上分析をする」「RFM分析をする」「ユーザーの訪問頻度を集計する」「継続率・定着率を分析する」など現場で頻出するパターンの紹介やクエリ例が掲載されており、非常に実践的です。サンプルデータのダウンロードもできるのでただ読むだけでなく実際に手を動かしながら学べるのもGOOD!
▼書籍概要
| 書籍名 | ビッグデータ分析・活用のためのSQLレシピ |
| 発売日 | 2017/3/27 |
| 著者 | 加嵜 長門、田宮 直人 |
| ページ数 | 496ページ |
| 出版社 | マイナビ出版 |
| 本の概要・おすすめポイント | 本書は名前の通りSQLをデータ分析に活用したい人のための必読書として人気がある書籍です。特徴は実務でデータ分析をする上で必要なケースが多数掲載されている点で、例えば「ECサイトの売上分析をする」「RFM分析をする」「ユーザーの訪問頻度を集計する」「継続率・定着率を分析する」など現場で頻出するパターンの紹介やクエリ例が掲載されており、非常に実践的です。サンプルデータのダウンロードも可能。 |
| 中身(目次) | 1 ビッグデータ時代に求められる分析力とは 2 本書で扱うツールとデータ群 3 データ加工のためのSQL 4 売上を把握するためのデータ抽出 5 ユーザーを把握するためのデータ抽出 6 Webサイトでの行動を把握するためのデータ抽出 7 データ活用の精度を高めるための分析術 8 データを武器にするための分析術 9 知識に留めず行動を起こす |
| 読んだ人のクチコミ | ・データ分析を強みにしたプロダクトマネージャーになりたいなら必読 ・実践的な分析テクニックが紹介されておりとても勉強になります ・ビッグデータエンジニア、アナリスト、プロダクトマネージャーなどデータを使う多くの職種で有用だと思います ・現場で「こういう分析がしたいけどどういうSQLを書けばいいのか」というときに辞書的に利用できて便利 |
購入はこちら
アジャイルサムライ
アジャイル開発を学ぶならこれを読め。そう言われることも多いのが、この「アジャイルサムライ」です。本格的なアジャイルプロジェクトを進めて、よりよいプロダクト開発、プロダクトマネジメントをしていきたい方はぜひご一読ください。
▼書籍概要
| 書籍名 | アジャイルサムライ |
| 発売日 | 2011/7/16 |
| 著者 | Jonathan Rasmusson、西村 直人、角谷 信太郎、近藤 修平 (翻訳), 角掛 拓未 (翻訳) |
| どんな人におすすめか | アジャイル開発を学びたいプロダクト開発者/PdM、開発プロセスを見直したい人 |
| 中身(目次) | 第I部 「アジャイル」入門 第1章 ざっくりわかるアジャイル開発 第2章 アジャイルチームのご紹介 第II部 アジャイルな方向づけ 第3章 みんなをバスに乗せる 第4章 全体像を捉える 第5章 具現化させる 第III部 アジャイルな計画づくり 第6章 ユーザーストーリーを集める 第7章 見積り:当てずっぽうの奥義 第8章 アジャイルな計画づくり:現実と向きあう 第IV部 アジャイルなプロジェクト運営 第9章 イテレーションの運営:実現させる 第10章 アジャイルな意思疎通の作戦 第11章 現場の状況を目に見えるようにする 第V部 アジャイルなプログラミング 第12章 ユニットテスト:動くことがわかる 第13章 リファクタリング:技術的負債の返済 第14章 テスト駆動開発 第15章 継続的インテグレーション:リリースに備える |
| 読んだ人のクチコミ | ・アジャイル開発をする際の必読書です ・アジャイルなプロダクト開発チームを作りたい人や組織にオススメ ・プロダクトマネージャーや開発ディレクターなどの指揮する人にはぜひ読んでほしいです |
エンジニアリング組織論への招待
「不確実性の取り扱い」これを学ぶのに最適な一冊がこちらの「エンジニアリング組織論への招待」です。プロダクトマネージャーはエンジニアやデザイナーなどのエンジニアリング組織と協働する職種ですし、実際に本書を必読書としてあげている経験豊富なプロダクトマネージャーやスタートアップ経営者も多いです。
※本書は「エンジニアのおすすめ本・参考書まとめ〜初心者の必読書・中級者向けなど〜」や「アジャイル開発・スクラムのおすすめ本ランキング(2024年)」、「組織・組織論のおすすめ本・書籍ランキング〜定番、入門書、名著など〜」でも紹介しています^^
▼書籍概要
| 書籍名 | エンジニアリング組織論への招待 |
| 発売日 | 2018/2/22 |
| 著者 | 広木 大地 |
| どんな人におすすめか | ソフトウェア開発/プロダクト開発に従事するエンジニア、プロダクトマネージャー、スタートアップなどの経営者 |
| 中身(目次) | Chapter 1 思考のリファクタリング Chapter 2 メンタリングの技術 Chapter 3 アジャイルなチームの原理 Chapter 4 学習するチームと不確実性マネジメント Chapter 5 技術組織の力学とアーキテクチャ |
| 読んだ人のクチコミ | ・少し内容的には難しいですが頑張って読み込む価値がある一冊 ・プロダクトマネージャーがエンジニアチームを指揮する上で心の支えになります ・後半のアジャイルなソフトウェア開発プロセスは一読の価値あり |
マーケティング・UX
プロダクトマネージャーはプロダクトを要件定義してディレクションすることだけが仕事というわけではありません。そもそも「何をつくるべきか」「誰に価値を届けるか」「どんな価値を届けるか」などプロダクトそのものを定義する役割でもあります。さらに、会社によってはその後のグロース・アクイジションなども担当する必要がある大変な職種です。
このセクションでは、そういったユーザー調査の手法であったり、ユーザーグロースに関連する書籍のおすすめを紹介していきます!(マーケティングのおすすめ本ランキング!名著から初心者向けまでも参考にしてください^^)
顧客起点マーケティング
プロダクトマネージャーにおすすめのマーケティング関連本の1冊目はこちらの『顧客起点マーケティング』です!「マーケティングでおすすめの本はなんですか?」と聞かれたらまっさきに推薦したいほどです。元P&Gやロート製薬、スマートニュースなどで活躍したマーケッター西口氏の著書で、5セグマップや9セグマップを活用した自社分析や競合分析などが非常に実務でも使えます。まだ読んでいない方は必読の一冊です。もちろん、N1インタビューやアンケート調査の手法なども紹介されており、網羅性も高いです。「【書評・要約】『顧客起点マーケティング』はビジネスマンの必読書だ」や「マーケティングのおすすめ本ランキング!名著から初心者向けまで」でも紹介しています。
▼書籍概要
| 書籍名 | たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング |
| 発売日 | 2019/4/8 |
| 著者 | 西口 一希 |
| どんな人におすすめか | プロダクトマネージャー、事業開発担当、スタートアップなどの経営者 |
| 中身(目次) | 序章 顧客起点マーケティングの全体像 第1章 マーケティングの「アイデア」とN1の意味 第2章 基礎編 顧客ピラミッドで基本的なマーケティング戦略を構築する 第3章 応用編 9セグマップ分析で販売促進とブランディングを両立する 第4章 ケーススタディ スマートニュースのN1分析とアイデア創出 第5章 デジタル時代の顧客分析の重要性 |
| 読んだ人のクチコミ | ・マーケティング本は定量分析に寄りがちですが、1人の顧客を具体的に観るという考え方が大変参考になりました ・概念的ではなく、実務的な内容が書かれておりとても勉強になります。実際に9セグマップをプロダクト戦略策定時に活用させていただきました ・プロダクトマネージャーなどの企画職に関わらず、経営者、デザイナー、開発者などプロダクト作りに関わる人すべてに読んでほしい実務書です。 |
トラクション ―スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル
プロダクトが素晴らしくてもトラクションを獲得できなければ死んでしまいます。トラクションとは顧客需要を表す定量的な「証し」や「成長する兆し」の指標です。本書『トラクション ―スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル』では、ユーザーを獲得するチャネルは様々ありますが、それらを19個紹介してくれています。また、どのチャネルが効果が高そうか?などを客観的に評価するブルズアイフレームワークという枠組みも提供してくれているため、チームでの議論にも使える一冊です。メガベンチャーですとPMMの役割かもしれませんが、スタートアップや新規事業担当にとっては必読かと思います。
▼書籍概要
| 書籍名 | トラクション ―スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル |
| 発売日 | 2015/5/23 |
| 著者 | ガブリエル・ワインバーグ、ジャスティン・メアーズ、和田 祐一郎 (翻訳) |
| どんな人におすすめか | プロダクトマネージャー、プロダクトマーケター、事業開発担当、スタートアップなどの経営者 |
| 中身(目次) | 目 次 I部 イントロダクション 1章 トラクションチャネル II部 トラクション獲得計画 2章 ブルズアイ・フレームワーク 3章 トラクション獲得の心構え 4章 トラクション獲得テスト 5章 最短経路 III部 19のトラクションチャネル 6章 バイラルマーケティング 7章 PR 8章 規格外 PR 9章 SEM 10章 ソーシャル /ディスプレイ広告 11章 オフライン広告 12章 SEO 13章 コンテンツマーケティング 14章 メールマーケティング 15章 エンジニアリングの活用 16章 ブログ広告 17章 ビジネス開発(パートナーシップ構築) 18章 営業 19章 アフィリエイトプログラム 20章 Webサイト、アプリストア、SNS 21章 展示会 22章 オフラインイベント 23章 講演 24章 コミュニティ構築 |
| 読んだ人のクチコミ | ・具体的なマーケティング施策を設計するフレームワークや事例まで掲載されており大変参考になります ・プロダクト立ち上げ前〜立ち上げ後のどのフェーズでも応用できる考え方のベースがわかります。 ・プロダクト集客をどうすべきか悩んでいるときに本書を読みました。プロダクトマネージャーと一緒に、本書で紹介されている19のトラクションチャネルを1つずつ「この施策は我々には当てはまるか?」とチェックしていき、戦略に落とし込むことができました |
Lean Analytics ―スタートアップのためのデータ解析と活用法
本書は「リーンスタートアップ」が提唱する構築・計測・学習ループの「計測」にフォーカスした本の『Lean Analytics ―スタートアップのためのデータ解析と活用法』です。特に秀逸なのが6つのビジネスモデル×事業のステージごとにどの指標を計測すべきか?ということが学べる点です。実際に、追いかけるKPIによって、チームでのアクションも大きく変動するため、「何をカイゼンするか」を決めるのはプロダクトマネジメントを行う上で非常に重要です。
▼書籍概要
| 書籍名 | Lean Analytics ―スタートアップのためのデータ解析と活用法 |
| 発売日 | 2015/1/24 |
| 著者 | アリステア・クロール、ベンジャミン・ヨスコビッツ、林 千晶、エリック・リース、角 征典 (翻訳) |
| どんな人におすすめか | プロダクトマネージャー、スタートアップの経営者、データ分析を強みにしたいプロダクトマネージャーやディレクター |
| 中身(目次) | 第1部 自分にウソをつかない 第2部 今すぐに適切な指標を見つける 第3部 評価基準 第4部 リーンアナリティクスを導入する |
| 読んだ人のクチコミ | ・すべてのプロダクト開発に関わる人が読むべき本です。どのようなメトリクス(数字)をKPIに持つべきか?改めて考えるキッカケになります ・ECサイト、SaaS、モバイルアプリ、メディアサイト、ユーザー生成コンテンツ、マーケットプレイス、などビジネスモデルごとに管理すべき指標が一覧化されており、とてつもなく参考になりました |
マッピングエクスペリエンス
こちらはプロダクトマネジメント、デザイン、サービス開発などに関わる人が読んでおきたい一冊です。特にUX検討する上で役立つツールである、サービスブループリント、カスタマージャーニーマップ、エクスペリエンスマップ、メンタルモデルダイアグラム、空間マップ/エコシステムモデルなどの主要なダイアグラムの紹介と使い方などの説明がされています。ユーザーに対するあらゆるタッチポイントで一貫性を持った体験を作る上で、組織の共通認識となるマップを作っておくことは非常に重要なので、ぜひ読んだ上で作ってみてください。
ノンデザイナーズ・デザインブック
プロダクトマネージャーも最低限のデザイン素養は必要です。こちらは企画職や開発職などの非デザイナー向けの書籍で、デザインの「4つの基本原則」など伝わる資料の原則を知ることができます。プロダクトに対してはもちろん、それ以外にも他人を巻き込んでいくためのドキュメント作成の機会がプロダクトマネージャーは多いため、常に手元においておきたい一冊です。
※本書は「デザインのおすすめ本・参考書ランキング〜初心者向け入門書など〜」でも紹介しています^^
予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」
行動経済学を学びたいなと思っていたときに、他のプロダクトマネージャーがおすすめしていた本だったので読みました。こちらは人間の行動は不合理であることを事例やデータを交えて説明してくれます。滑稽な事例、身近な事例も多くでてくるので、楽しく読めるかもしれません。
※本書は「経済・経済学のおすすめ本・書籍ランキング〜定番、入門書など幅広く紹介!〜」や「行動経済学の本・書籍ランキング23選」でも紹介している良書です^^
行動を変えるデザイン
こちらも前述の予想通りに不合理と一緒に、心理学や行動経済学を学びたいと思っててにとった一冊です。人間がどのように意思決定しているのか(認知メカニズム)を説明し、その上でどのように行動を変えていくのか?という具体的な施策までCREATEフレームワークを使って一気通貫で解説をしてくれています。デジタルサービス、デジタルプロダクト開発に携わる方は読んでおきたいです。
ついやってしまう体験のつくりかた
こちらは元任天堂の企画開発者の方による、優れたサービスやプロダクトのつくりかたの本です。どうすれば人の心を動かして「ついやってしまう」体験をデザインできるのか?
仮説→施行→歓喜という「直感のデザイン」を連続でつないで少しずつプレイヤーを没頭させていく。ほかにも「驚きのデザイン」「物語のデザイン」などの手法を、マリオ、ドラクエ、ポケモン、テトリスなどの超有名ゲームの事例を踏まえて解説してくれています。
もちろん、ゲーム以外のプロダクトにも応用できる根本的な考え方なので、C向けサービスのあらゆる業界のプロダクトマネージャーにおすすめしたい本です。
※本書は「企画力を高めるためのおすすめ本 〜定番本、アイデア、商品企画、コンセプト、企画書など〜」でも紹介しています^^
▼書籍概要
| 書籍名 | 「ついやってしまう」体験のつくりかた 人を動かす「直感・驚き・物語」のしくみ |
| 対象者 | 商品やサービスの企画開発に携わる社会人やビジネスパーソン、特にクリエイターやプランナーに最適です。新しいアイデアを生み出し、ユーザーの行動を促す方法を学びたいと考えている方におすすめです。 |
| ひとこと説明 | 元任天堂「Wii」の企画担当者が解説する体験デザイン(UX)入門。人の心を動かし行動させる仕組みと仕掛けを明らかにし、企画・開発・マーケティング・営業に幅広く役立つ内容を提供します。 |
| 著者 | 玉樹 真一郎 (著) |
| 発売日 | 2019/8/8 |
| ページ数 | 328ページ |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| 中身(目次) | 第1章 人はなぜ「ついやってしまう」のか 第2章 人はなぜ「つい夢中になってしまう」のか 第3章 人はなぜ「つい誰かに言いたくなってしまう」のか 終章 私たちを突き動かす「体験→感情→記憶」 |
| 読んだ人のクチコミ | ・具体的な事例が豊富で、実際のビジネスにすぐに役立つ内容が満載でした。新しい視点からのアプローチがとても参考になります。 ・視点を変えることで新しい価値が生まれることを実感しました。企画の基本から応用まで網羅されていて非常に実用的です。 ・企画書の作成方法だけでなく、説得力を持たせるためのプレゼンテーション技術も学べる点が良かったです。実践的なアドバイスが多くて助かりました。 |
ハマる仕掛け
こちらもC向けサービスのプロダクトマネジメントをする上で必須となる「Hook model」を学べる本です。あらゆる成功したスタートアップが当てはまる、行動心理学とデザインで裏打ちされたフレームワークとして人気がある本です。トリガー、アクション、リワード、インベストメンドという4つの領域で、それぞれ施策や機能を考える型にもなるので、ぜひ一読をおすすめしたいです。
ユーザビリティエンジニアリング
UXの教科書としてプロダクトマネージャーやUXデザイナーに支持されている名著がこちらの「ユーザビリティエンジニアリング(第2版) ―ユーザエクスペリエンスのための調査、設計、評価手法―」です。ユーザビリティ工学が専門で特にユーザ調査とユーザビリティ評価の実務経験・実績が豊富な利用品質ラボ代表の樽本徹也氏による著書です。インタビュー、プロトタイプ、定性調査、ヒューリスティック評価、ユーザーテストなど優れたUXをつくる上で役に立つツールの紹介が豊富です。著者の樽本さんは今のようにUX・利用品質がもてはやされる前から第一線で活躍されており、権威として有名です。(私も10年ほど前に事務所にお邪魔させていただきましたが、とても面白い方でした笑)
※ユーザーインタビューのおすすめ本!現役UXリサーチャーが厳選でも紹介しています
▼書籍概要
| 書籍名 | ユーザビリティエンジニアリング(第2版) ―ユーザエクスペリエンスのための調査、設計、評価手法― |
| ジャンル | ユーザーインタビュー特化 |
| ひとこと説明 | UXやユーザーインタビューなどを学びたいときの名著的な一冊 |
| 著者 | 樽本 徹也 |
| 発売日 | 2014/2/26 |
| ページ数 | 256ページ |
| 出版社 | オーム社 |
| 中身(目次) | イントロダクション Chap1 ユーザ中心設計概論 Part1 調査 Chap2 インタビュー法 Chap3 インタビューの実践 Chap4 データ分析法 Part2 設計 Chap5 発想法 Chap6 プロトタイプ Part3 評価 Chap7 ユーザビリティ評価法 Chap8 ユーザテスト Chap9 ユーザテストの準備 Chap10 ユーザテストの実施 Chap11 分析と再設計 エンディング Chap12 ユーザ中心設計活動 |
| 読んだ人のクチコミ | ・基礎知識や考え方はもちろん、実務での進め方まで詳細にかかれており、非常に参考になりました ・ユーザビリティやUX改善を考える人にとってバイブル的な一冊です。内容が非常に具体的で実務的です。よくある概念的な考え方を紹介するだけの書籍とは全然違う充実度です ・樽本さんのファンです(笑)インタビューの章がとても参考になりました |
購入はこちら
ビジネス全般
次のセクションはビジネス全般です。プロダクトマネジメントに限らず、基本的にビジネスマンであれば抑えておきたいロジカルシンキングやドキュメンテーションなどのベーススキルからはじまり、事業計画策定やチームマネジメントなど、幅広い分野を紹介していきます。名著と呼ばれるものが多いですが、それだけ普遍的で有益な内容が詰まっているということですね。それでは順番にご紹介します!
イシューからはじめよ
言わずとしれた名著イシューからはじめよです。過去に上司からおすすめされて読みました。本書は圧倒的に生産性が高い人に共通する問題設定&解決方法が学べる書籍です。発売から10年経ちますが、今でもビジネスパーソンが読むべきおすすめ本にランクインすることが多い名著です。まずは根本に関わる問題をみつけることからはじめなさいという教えです。解くべき問いが間違っていたら、どれだけ頑張って解決しても、全く価値を産まないためですね。犬の道に陥ってしまうと社会人として必要なバリューも出せないので、ぜひ本書で仕事の基礎・基本を見に付けてください!こちらはプロダクトマネジメントする上で必須の考え方になるので、何度も読み返したい一冊です。
※本書は「ロジカルシンキング・論理的思考力のおすすめ本・書籍ランキング」や「新卒・新社会人が読むべきおすすめ本ランキング」でも紹介しています^^
良い戦略、悪い戦略
戦略を考える上で最も良い本だと思ったのが、こちらの『良い戦略、悪い戦略』です。こういう戦略が良い戦略ですよという良い事例の説明はもちろん、間違った悪い戦略の事例も解説してくれるので、「あ、これ自分たちもやっちゃってるな」という気づきを得られるようになっています。プロダクト企画をするとどうしてもやりたいことが増えてしまうのですが、やっぱり一番大事なのは「やらないことを決める」だと思いました。
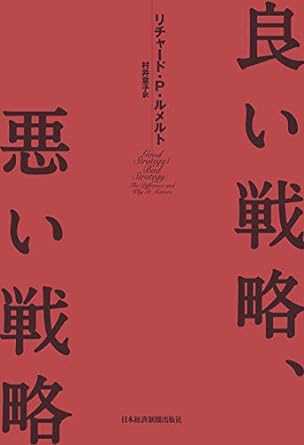
※本書は「コンサルタントのおすすめ本〜必読書、論理思考、問題解決、戦略策定、面接対策など〜」や「「戦略」を学びたい人におすすめ本ランキング!良書・名著を厳選」などでも紹介しています。
▼書籍概要
| 書籍名 | 良い戦略、悪い戦略 |
| 発売日 | 2012/6/23 |
| 著者 | リチャード・P・ルメルト、村井章子 (翻訳) |
| ページ数 | 421ページ |
| 出版社 | 日経BP |
| 本の概要・おすすめポイント | 「良い戦略とはどういうもので、悪い戦略とはどういうものである」というのが詳しく解説されています。フレームワークをいくら学んでも身につかない戦略についての深い洞察を得たいならぜひおすすめ。戦略系書籍として最も推薦できます! |
| 中身(目次) | 序章 手強い敵 第1部 良い戦略、悪い戦略 第1章 良い戦略は驚きである 第2章 強みを発見する 第3章 悪い戦略の四つの特徴 第4章 悪い戦略がはびこるのはなぜか 第5章 良い戦略の基本構造 第2部 良い戦略に活かされる強みの源泉 第6章 テコ入れ効果 第7章 近い目標 第8章 鎖構造 第9章 設計 第10章 フォーカス 第11章 成長路線の罠と健全な成長 第12章 優位性 第13章 ダイナミクス 第14章 慣性とエントロピー 第15章 すべての強みをまとめる―NVIDIAの戦略 第3部 ストラテジストの思考法 第16章 戦略と科学的仮説 第17章 戦略思考のテクニック 第18章 自らの判断を貫く |
| 読んだ人のクチコミ | ・タイトルの通り、良い戦略、悪い戦略、について凄く理解できました。私の会社でも悪い戦略を作ってないか?改めて考えるキッカケになりました ・悪い戦略についての洞察が深い。ストーリーとしての競争戦略も良かったが本書も同レベルで勉強になりました。 ・新規事業戦略やプロダクト戦略においても活用できる内容。非常に良書。 ・ビジネスの現場で頻繁にでてくる戦略という言葉の本質的な部分を理解できました |
購入はこちら
解像度を上げる
「解像度」という言葉はビジネスの場で使われる機会が増えてきました。ふわっとしていて抽象的、ぼんやりしている、具体性がない、などのときに「解像度が低い(粗い)」などと言い、考えや説明が明晰で具体的、シャープなときに「解像度が高い」などと言います。
本書「解像度を上げる」では、そういった思考を明晰にするための方法について非常に解像度高く、具体的に解説してくれています!事業開発やプロダクトマネジメントに取り組む上でも非常に重要なポイントとなっており、ぜひ読んでみてください。Youtubeで著者による「解像度を高める」という動画もでているので、そちらも参照ください^^
※本書は「思考力のおすすめ本・書籍ランキング〜定番、名著、入門書など幅広く紹介!〜」でも紹介している良書です^^
▼書籍概要
| 書籍名 | 解像度を上げる――曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法 |
| 発売日 | 519ページ |
| 著者 | 馬田隆明 |
| ページ数 | 2022/11/19 |
| 出版社 | 英治出版 |
| 本の概要・おすすめポイント | 「ふわっとしている・既視感がある・ピンとこない」など言われたときは解像度が粗い可能性があります。解像度が高い人、低い人はどういう特徴があるのか?どのようにすれば解像度を高めることができるのか?深さ、広さ、構造、時間の4つの視点から解像度を高める方法を解説していきます |
| 中身(目次) | 第1章 解像度を上げる4つの視点 第2章 あなたの今の解像度を診断しよう 第3章 型を意識しながら、まず行動からはじめて、粘り強く取り組み続ける 第4章 課題の解像度を上げる―「深さ」 第5章 課題の解像度を上げる―「広さ」「構造」「時間」 第6章 解決策の解像度を上げる―「広さ」「構造」「時間」 第7章 実験して検証する 第8章 未来の解像度を上げる |
| 読んだ人のクチコミ | ・解像度が高いとはどういう状態なのか?解像度という言葉そのものの解像度を高めて、その上で事業の解像度を高める方法まで深く理解できる良書です ・深さ、広さ、構造、時間、を駆使して解像度を高めるためのノウハウが詰まっています。ベストセラーに近い売れ行きなのが納得です ・馬田さんのスライドで入門した者です。より詳細に学びたいので書籍を読みましたら正解でした!スライドの内容をより解像度高く理解することができました ・新規事業や新規プロダクトを創るときにも解像度を高めることが非常に重要だとわかりました |
購入はこちら
ハイアウトプット マネジメント
こちらの「ハイアウトプットマネジメント(HIGH OUTPUT MANAGEMENT)」はインテル元CEOのアンディ・グローブ氏による著書でマネージャー向けの本です。書かれたのは40年以上前ですが。表面的ではなく本質的な内容なので40年経っても全く色褪せない名著です。自分も管理職として一皮向けたいなと思ったときに読んで「もっと早く読んでおけば良かった!」と思いました。自分ではモノを作れない職業であるプロダクトマネージャーに必要となる、アウトプットを最大化するための基本原理、マネージャーが注力すべき仕事、1on1のやりかた、などが書かれています。「【書評・要約】『ハイアウトプット マネジメント』で学んだマネージャーの心得」で要約・書評記事を公開しています。また、「管理職のおすすめ本ランキング22冊!マネジメントを勉強しよう」でも紹介しています!
▼書籍概要
| 書籍名 | ハイアウトプットマネジメント(HIGH OUTPUT MANAGEMENT) |
| 発売日 | 2017/1/11 |
| 著者 | アンドリュー・S・グローブ、小林 薫 (翻訳) |
| 本の概要 | インテル元CEOのアンディ・グローブ氏による著書でマネージャー向けの本です。自分ではモノを作れない職業であるプロダクトマネージャーに必要となる、アウトプットを最大化するための基本原理、マネージャーが注力すべき仕事、1on1のやりかた、などが書かれています。マネージャー向けの名著です。 |
| どんな人におすすめか | ・初めてプロダクトマネージャーになった人 ・管理職として一皮向けたい人 ・チームで成果を出すには何をすれば良いのか知りたい人 |
| おすすめポイント | アウトプットを最大化するための基本原理、マネージャーが注力すべき仕事、1on1のやりかた、などマネージャーに必要な考え方や知識が詰まっています。内容も具体的で事例もあるので抽象的な概念本とは違う深い理解をすることができます。 |
| 中身(目次) | 第1部 朝食工場ー生産の基本原理 1章 生産の基本 2章 朝食工場を動かす 第2部 経営管理はチーム・ゲームである 3章 経営管理のテコ作用 4章 ミーティング 5章 決断、決断、また決断 6章 計画化 第3部 チームの中のチーム 7章 朝食工場の全国展開へ 8章 ハイブリッド組織 9章 二重所属制度 10章 コントロール方式 第4部 選手たち 11章 スポーツとの対比 12章 タスク習熟度 13章 人事考課 14章 二つの難しい仕事 15章 タスク関連フィードバックとしての報酬 16章 なぜ教育訓練が上司の仕事なのか |
| 読んだ人のクチコミ | ・マネージャーとしてのアウトプットを高めるためには「テコを使う」という表現がとてもしっくり来ました。また、情報収集がとても大事であるという点も納得感があり、実際に日々の業務でとても意識しています ・人事考課を軽視していましたが、しっかりとやらなければいけないと肝に命じます。また、部下に対して何を期待しているのかを日々1on1で伝え続ける重要性もよく理解できました。この本は何度も読み返したいです! |
BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?
プロダクトマネージャーはプロジェクトマネジメントをする機会も多いと思います。本書『BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?』は、大規模プロジェクトマネジメントの第一人者であるベント・フリウビヤとダン・ガードナーが、メガプロジェクトを成功に導くための戦略やスキルを紹介しています。限られた予算や厳しい期限の中でどのようにして莫大な利益を生むのか、また失敗を回避するために必要な「慎重な計画」と「素早い実行」のバランスを解説しています。企業リーダーやプロジェクトマネージャーに向けて、成功を確実にするための具体的な方法論を提供しており、大変参考になる内容です!!
▼書籍概要
| 書籍名 | BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか? |
| 対象者 | 企業の経営層やプロジェクトマネージャー、大規模なプロジェクトを手掛ける人、戦略的な意思決定を行うリーダーに向けた内容です。実践的な知識を持ち、プロジェクト管理の経験がある人に特に適しています。 |
| ひとこと説明 | メガプロジェクトを成功に導くための戦略を、実践的な知見と共に解説する一冊 |
| 著者 | ベント・フリウビヤ (著)、ダン・ガードナー (著)、櫻井 祐子 (翻訳) |
| 発売日 | 2024/4/24 |
| ページ数 | 400ページ |
| 出版社 | サンマーク出版 |
| 中身(目次) | 序章 “夢のカリフォルニア”―ビッグアイデアの生死の境目 1章 ゆっくり考え、すばやく動く―「じっくり計画」が成功の鍵 2章 本当にそれでいい?―「早く決めたい」衝動に賢く抗う 3章 「根本」を明確にする―目的がくっきり頭にあれば間違った道具は取らない 4章 ピクサー・プランニング―アイデアは「灰色のモヤモヤ」から始まる 5章 「経験」のパワー―最初から「貯金」がある状態で始める 6章 唯一無二のつもり?―想像との「ズレ」をなくす 7章 再現的クリエイティブ―「創造はロマン」vs「創造は管理できる」 8章 一丸チームですばやくつくる―「一体感」で全員の士気を高める 9章 スモールシング戦略―小さいものを積み上げて巨大にする 終章 「見事で凄いもの」を創る勝ち筋―メガプロジェクト研究が導く11の経験則 |
| 読んだ人のクチコミ | ・計画の重要性と慎重さについて深く考えさせられました。多くのプロジェクトが抱える問題を克服するための具体的な方法が参考になります。 ・ピクサーの事例や「根本」を見失わない姿勢が印象的で、プロジェクト管理だけでなく日常業務にも応用できる内容です。 ・メガプロジェクトを成功させるためのアイデアが満載で、リーダーシップやチームビルディングにも役立つ一冊です。 ・プロジェクトの初期段階で時間をかけることの重要性がよく理解できました。短期的な成功ではなく、長期的な視点での計画が鍵です。 ・非常に実践的でありながら、理論も充実しているため、読み応えがあります。リーダーやマネージャーに特におすすめです。 |
購入はこちら
世界一流エンジニアの思考法
次はエンジニアだけではなくプロダクトマネージャーにもおすすめの『世界一流エンジニアの思考法』です!マイクロソフトでエンジニアとして活躍する著者が、マイクロソフトで活躍している一流のエンジニアの思考法を明かしたものです。単なる技術的なスキルではなく、思考の習慣、時間管理、生産性向上のための具体的な手法を中心に取り上げています。特に「失敗から学ぶ」重要性や、効率を重視した仕事の進め方、無駄を省くための考え方が印象的です。
※本書は「タスク管理・ToDo管理のおすすめ本・書籍ランキング〜定番、入門書など〜」でも紹介している良書です^^
▼書籍概要
| 書籍名 | 世界一流エンジニアの思考法 |
| 対象レベル | プロダクトマネージャー |
| ひとこと説明 | 一流エンジニアの思考法を通して、生産性向上と効率化の秘訣を学べる一冊。挑戦と失敗を恐れずに成長するための実践的な指南書 |
| 著者 | 牛尾 剛 |
| 発売日 | 2023/10/23 |
| ページ数 | 272ページ |
| 出版社 | 文藝春秋 |
| 中身(目次) | 第1章 世界一流エンジニアは何が違うのだろう?―生産性の高さの秘密 第2章 アメリカで見つけたマインドセット―日本にいるときには気づかなかったこと 第3章 脳に余裕を生む情報整理・記憶術―ガチで才能のある同僚たちの極意 第4章 コミュニケーションの極意―伝え方・聞き方・ディスカッション 第5章 生産性を高めるチームビルディング―「サーバントリーダーシップ」「自己組織型チーム」へ 第6章 仕事と人生の質を高める生活習慣術―「タイムボックス」制から身体づくりまで 第7章 AI時代をどう生き残るか?―変化に即応する力と脱「批判文化」のすすめ |
| 読んだ人のクチコミ | ・具体的な思考法や生産性の高め方が非常に参考になった。特に、フィードバックを歓迎する文化を作る重要性に気づかされた ・完璧主義を捨て、20%の仕事に集中する考え方は目から鱗。仕事の進め方を見直す良いきっかけになった。PMとしてやるべきことを盛り込みがちになるが、本当に大事なことにフォーカスすべきだと痛感させられました ・エンジニアだけでなく、プロダクトマネージャーにも適した内容。思考の整理と時間管理法が役立った |
購入はこちら
Google流資料作成術
資料作成スキルを養える良書の1つが「Google流資料作成術」です。
本書はGoogle社員が伝授する資料作成術を解説した本です。データだけでなくストーリーも重視し、シンプルかつ分かりやすく伝える方法が示されています。豊富な事例やビジュアルと共に、実践的なノウハウが紹介されており、誰でもすぐに実践できる内容となっており、資料作成の機会が多いプロダクトマネージャーなどのビジネスマンにおすすめの一冊です^^
※本書は「資料作成のおすすめ本・書籍ランキング〜定番、入門書、初心者向けなど〜」でも紹介しています^^
▼書籍概要
| 書籍名 | Google流資料作成術 |
| 対象者 | 資料作成スキルを高めたい人、人に伝えるグラフや図の作成方法を学びたい人。ビジネスやプレゼンテーション資料を作成するビジネスパーソンやプロフェッショナル、データ分析や情報提供に携わるコンサルタント |
| ひとこと説明 | 資料作成本として全米でベストセラーになった名著です |
| 著者 | コール・ヌッスバウマー・ナフリック (著), 村井瑞枝 (翻訳) |
| 発売日 | 2017/2/16 |
| ページ数 | 269ページ |
| 出版社 | 日本実業出版社 |
| 中身(目次) | 第1章 コンテキストを理解する 第2章 相手に伝わりやすい表現を選ぶ 第3章 不必要な要素を取りのぞく 第4章 相手の注意をひきつける 第5章 デザイナーのように考える 第6章 モデルケースを分解する 第7章 ストーリーを伝える 第8章 さあ、全体をまとめよう 第9章 ケーススタディ 第10章 最後に |
| 読んだ人のクチコミ | ・「データをもとにストーリーを語る」ことで、資料作成のプロセスと技術を紹介し、伝わる資料の作成方法を解説してくれる良書です ・データのストーリー化が実践的でわかりやすい。ビジュアルも豊富で、資料作成が格段に楽になった! |
購入はこちら
さて、かなりボリュームが増えてしまったので、これ以降はタイトルのみのご紹介とします!(今後準備して、説明と合わせて更新をしていきます)
・仮説思考
・論点思考
・考える技術・書く技術
・THE・TEAM
・ビジョナリー・カンパニー2
・マンガでやさしくわかる事業計画書
・具体と抽象
・事例・体験記
・zero to one
・トヨタの製品開発
・netflix(no rules)
・START UP
さいごに
▼【注目】Amazonが現在、タイムセールを開催中!
人気の商品が日替わりで登場!お得なタイムセールを実施中!(Amazon)
以上、プロダクトマネジメントを学ぶ上で参考になった本を紹介してきましたが、いかがでしたか?
冊数は多いのですが、それほどプロダクトマネージャーという職種のスキル領域が広いので、少しずつ身に着けていくのがおすすめです。
参考になった方はシェアやブックマークなど、ぜひお願いいたします!
※本サイトでは一部のコンテンツにプロモーションが含まれています
Twitterやってます

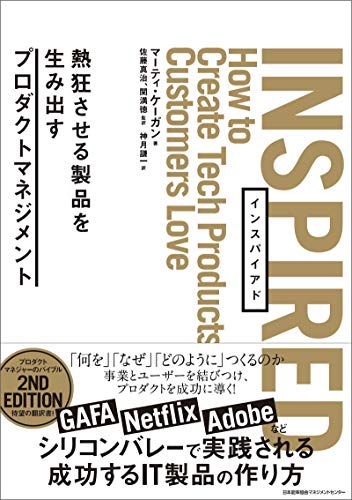

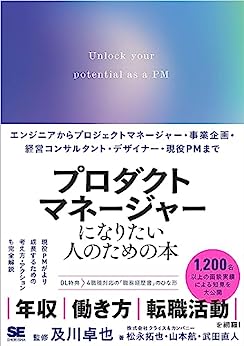
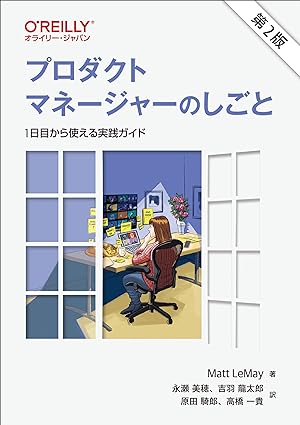



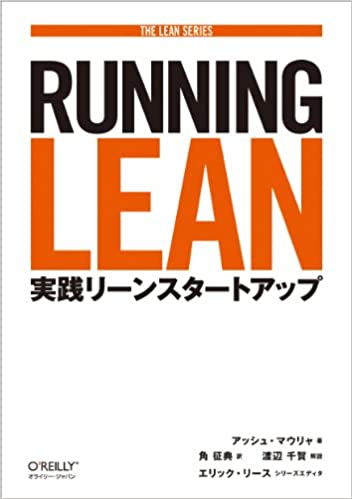
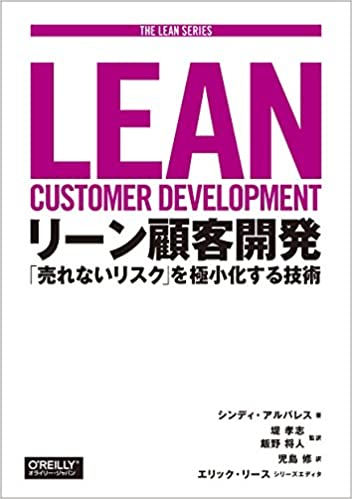

-795x1024.jpg)