労働経済学のおすすめ本・書籍ランキング〜初心者向け、入門書など〜
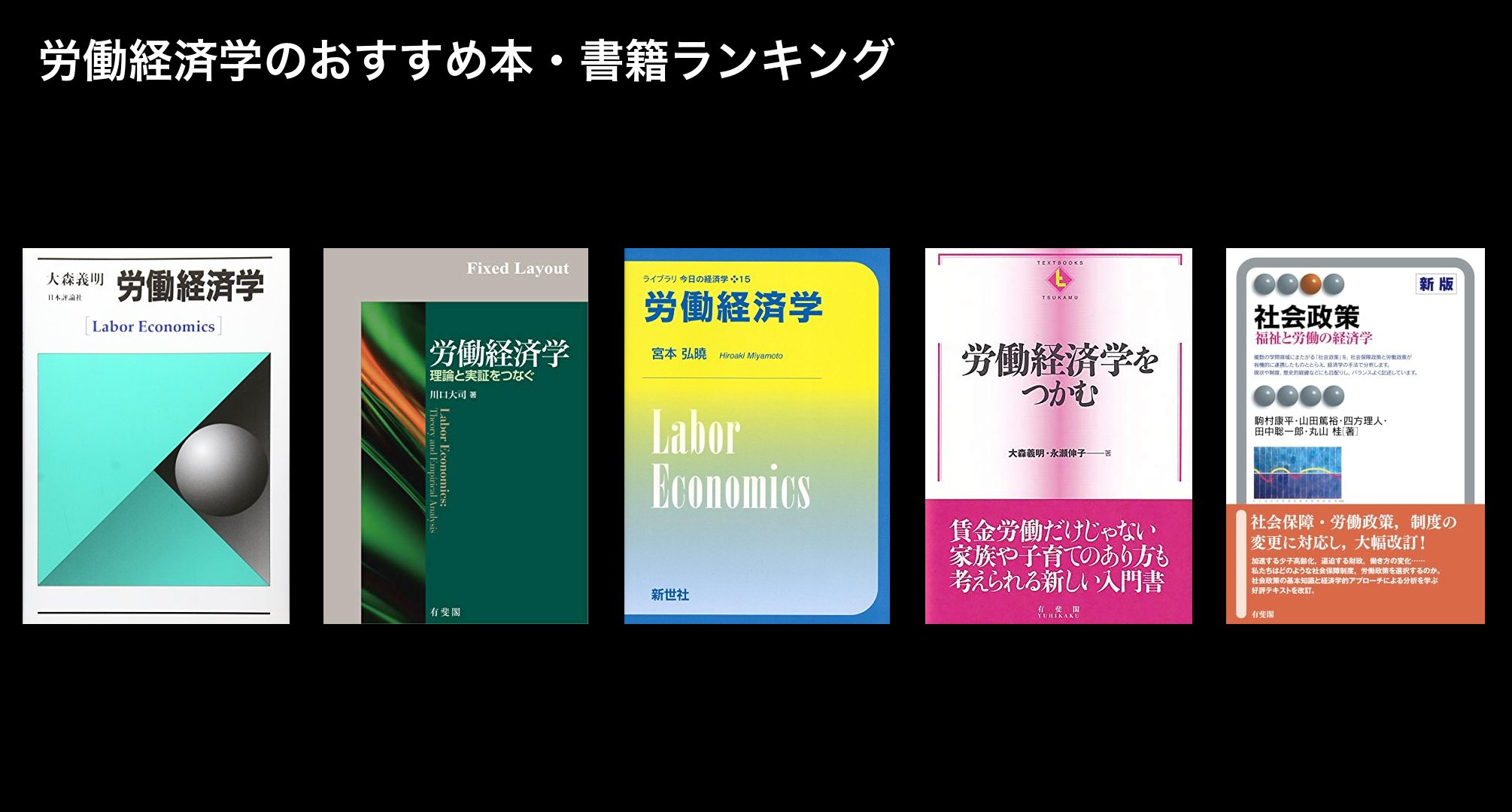
労働経済学は、働き方や雇用の仕組み、賃金の動きなど、私たちの身近な経済活動を理解するうえで重要な学問です。でも、初心者の方にとっては少し難しそうに感じることもあるでしょう。そこで今回は、労働経済学の入門書や初心者向けのおすすめ書籍をランキング形式でご紹介します。基礎からしっかり学べる一冊を見つけて、労働市場の仕組みを理解し、より良い働き方について考えてみませんか?ぜひ参考にしてください!
※本記事のランキングはウェブ上のクチコミ・評判・紹介数などを基準にサイト独自の基準に基づいて作成しております。また、一部のコンテンツにプロモーションが含まれています。
1位:労働経済学
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第1位は「労働経済学」です。

▼書籍概要
本書は労働経済学の基礎から応用までを丁寧に解説した一冊です。労働市場の仕組みや賃金決定のメカニズム、雇用の動向、労働政策の影響など、多角的な視点で分析しています。経済学の理論だけでなく、実際のデータやケーススタディも豊富に盛り込まれており、実務や研究に役立つ内容となっています。専門的な内容をわかりやすく解説しているため、経済学の知識を深めたいビジネスパーソンや研究者にとって有益です。労働市場の現状や未来展望を理解したい方に特におすすめの一冊です。
| 書籍名 | 労働経済学 |
| 対象者 | 経済や労働に関心のあるビジネスパーソンや研究者に最適。 |
| ひとこと説明 | 労働経済学の基本と最新動向を体系的に理解できる解説書。 |
| 著者 | 大森 義明 |
| 発売日 | 2008/03/22 |
| 出版社 | 日本評論社 |
| ページ数 | 243ページ |
| 価格 | ¥3,520 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
2位:労働経済学
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第2位は「労働経済学」です。

▼書籍概要
本書は労働経済学の基礎から応用までを体系的に解説した書籍で、理論と実証分析のバランスを重視しています。各章では理論の導入に続き、実証分析を紹介し、現実の労働市場の動向や制度の影響を深く理解できる構成となっています。経済学的な視点だけでなく、具体的なデータやケーススタディも豊富に盛り込まれており、労働市場の現状や課題を多角的に学べる一冊です。初心者から専門的に学びたい方まで幅広く対応し、実務に役立つ知識も得られるため、労働経済学を体系的に学びたい方にとって非常に価値ある内容です。
| 書籍名 | 労働経済学 |
| 対象者 | 経済学や労働市場の実務に関わる専門職や研究者に最適です。 |
| ひとこと説明 | 労働経済学の理論と実証分析をバランス良く解説した体系的な教科書。 |
| 著者 | 川口大司 |
| 発売日 | 2017/12/22 |
| 出版社 | 有斐閣 |
| ページ数 | 326ページ |
| 価格 | ¥3,018 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
3位:労働経済学 (ライブラリ今日の経済学 15)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第3位は「労働経済学 (ライブラリ今日の経済学 15)」です。

▼書籍概要
本書は労働経済学の基本的な理論や実証分析を丁寧に解説し、「働くこと」に関わるさまざまな問題に対して政策立案の視点を提供しています。雇用市場の構造や労働供給と需要の関係、賃金決定のメカニズム、労働市場の格差や失業問題など、実際の社会課題に基づいた内容を分かりやすく解説。経済学の知識を深めながら、現代の働き方や労働政策について理解を深める一冊です。労働経済学の基礎から応用まで幅広く学びたい方に最適です。
| 書籍名 | 労働経済学 (ライブラリ今日の経済学 15) |
| 対象者 | 経済・労働政策に関心のある専門家や研究者におすすめ。 |
| ひとこと説明 | 労働市場の仕組みと政策課題を体系的に理解できる労働経済学の入門書。 |
| 著者 | 宮本 弘曉 |
| 発売日 | 2018/04/01 |
| 出版社 | 新世社 |
| ページ数 | 288ページ |
| 価格 | ¥1,079 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
4位:労働経済学をつかむ (TEXTBOOKS TSUKAMU)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第4位は「労働経済学をつかむ (TEXTBOOKS TSUKAMU)」です。

▼書籍概要
本書は、労働経済学の基礎をわかりやすく解説しながら、従来の賃金や労働時間だけでなく、家庭やケア活動といった無償労働の視点も取り入れることで、働くことと暮らすことの関係性を深く理解できる一冊です。図表や具体的なデータを用いてモデルを丁寧に解説し、日本の労働市場が抱える課題や現状を、多角的に考察します。労働と生活の両面から社会の仕組みを見つめ直し、現代の働き方や政策に新たな視点を提供します。
| 書籍名 | 労働経済学をつかむ (TEXTBOOKS TSUKAMU) |
| 対象者 | 労働市場や社会政策に関心のある実務者や研究者に最適。 |
| ひとこと説明 | 働くことと暮らすことのつながりを多角的に解説した労働経済学の入門書。 |
| 著者 | 大森 義明, 永瀬 伸子 |
| 発売日 | 2021/04/08 |
| 出版社 | 有斐閣 |
| ページ数 | 283ページ |
| 価格 | ¥2,750 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
5位:社会政策〔新版〕: 福祉と労働の経済学 (有斐閣アルマ)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第5位は「社会政策〔新版〕: 福祉と労働の経済学 (有斐閣アルマ)」です。

▼書籍概要
本書は、社会保障制度や福祉政策を経済学の視点から分析し、その仕組みと変遷を理解するための一冊です。最新の医療保障改革や確定拠出年金法など、最近の制度改正に対応した内容が盛り込まれており、統計データも最新版にアップデートされています。社会政策を理論と実務の両面から学びたい方にとって、具体例や解説が丁寧で理解しやすく、政策の背景や経済的影響を深く知ることができます。福祉と労働の経済学に関心のある専門家や実務担当者にとっても、実践的な知識を得られる良書です。
| 書籍名 | 社会政策〔新版〕: 福祉と労働の経済学 (有斐閣アルマ) |
| 対象者 | 社会政策や福祉制度の専門家、経済学の実務者、政策立案者向け。 |
| ひとこと説明 | 社会保障制度の経済学的分析と最新動向を理解できる解説書。 |
| 著者 | 駒村 康平, 山田 篤裕, 四方 理人, 田中 聡一郎, 丸山 桂 |
| 発売日 | 2025/03/13 |
| 出版社 | 有斐閣 |
| ページ数 | 349ページ |
| 価格 | ¥2,970 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
6位:労働経済学入門 新版
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第6位は「労働経済学入門 新版」です。

▼書籍概要
本書は、日本の労働市場を取り巻くさまざまなトピックスをわかりやすく解説した労働経済学の入門書です。経済の基礎知識から労働政策、雇用の変動、労働者の働きがいといった重要なテーマを丁寧に解説しており、現代の不安定な時代背景を踏まえた働き方や暮らしの安定に役立つ内容となっています。実務や労働問題に関心のある方にとって、理論と実例をバランス良く学べる貴重な一冊です。複雑な経済用語もやさしく解説されているため、専門知識がなくても理解しやすくなっています。
| 書籍名 | 労働経済学入門 新版 |
| 対象者 | 労働市場の動きや経済的背景に関心のあるビジネスパーソンや研究者におすすめです。 |
| ひとこと説明 | 日本の労働経済と働き方の現状と課題をわかりやすく解説した入門書。 |
| 著者 | 太田 聰一, 橘木 俊詔 |
| 発売日 | 2012/02/22 |
| 出版社 | 有斐閣 |
| ページ数 | 224ページ |
| 価格 | ¥1,870 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
7位:労働と雇用の経済学
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第7位は「労働と雇用の経済学」です。

▼書籍概要
本書は、労働と雇用の経済学を理解するための入門書です。賃金の決まり方や労働時間、多様な働き方、高齢者や外国人労働者の現状など、複雑なテーマを経済学の専門用語を最小限に抑えつつ解説しています。数式を多用せず、現実の労働市場の動きや政策の背景をわかりやすく伝えることで、経済学の知識がない方でも理解しやすい内容となっています。実生活や社会問題に直結したテーマを扱い、働き方の多様化を理解したい方に最適です。
| 書籍名 | 労働と雇用の経済学 |
| 対象者 | 経済学の知識がなく、労働市場や働き方の現実を理解したいビジネスパーソンや社会人におすすめ |
| ひとこと説明 | 労働市場の基本と現実の働き方をわかりやすく解説した入門書 |
| 著者 | 永野 仁 |
| 発売日 | 2017/02/22 |
| 出版社 | 中央経済社 |
| ページ数 | 185ページ |
| 価格 | ¥2,640 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
8位:正規の世界・非正規の世界――現代日本労働経済学の基本問題
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第8位は「正規の世界・非正規の世界――現代日本労働経済学の基本問題」です。

▼書籍概要
本書は、現代日本の働き方を取り巻く正規・非正規の二つの世界を壮大なスケールで分析し、働き方改革の根底に潜む課題や未来のトレンドを詳述しています。幅広い分析手法を駆使し、労働経済学の視点から社会構造の変化や労働者の実態を明らかにしています。現状の問題点だけでなく、今後の働き方の方向性についても深く掘り下げており、政策立案者や経済関係者、労働者の理解促進に資する一冊です。読み応えのある内容と実践的な洞察が詰まった、労働経済学の重要書といえます。
| 書籍名 | 正規の世界・非正規の世界――現代日本労働経済学の基本問題 |
| 対象者 | 労働政策や経済学に関心のある専門家や実務者向け |
| ひとこと説明 | 日本の働き方の現状と未来を経済学的視点から解明した労働経済学の解説書。 |
| 著者 | 神林 龍 |
| 発売日 | 2017/11/08 |
| 出版社 | 慶應義塾大学出版会 |
| ページ数 | 444ページ |
| 価格 | ¥5,280 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
9位:「働くこと」を思考する
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第9位は「「働くこと」を思考する」です。

▼書籍概要
本書は、「働くこと」に関する多様なテーマを深く掘り下げ、外国人労働者や障害者、LGBT、結婚・育児、AIといった現代社会における働き方の変化や課題について具体的に解説しています。多様性を尊重し、共生を促進するための視点や実践的な考え方を提供し、働く人々がより良い職場環境を築くためのヒントが満載です。現代の労働環境に関心のあるビジネスパーソンや経営者にとって、役立つ知見と示唆に富んだ一冊です。
| 書籍名 | 「働くこと」を思考する |
| 対象者 | 多様な働き方や社会的背景に関心のあるビジネスパーソンや管理職層におすすめ。 |
| ひとこと説明 | 現代社会の多様性と働き方の未来を理解し、共生を促進するための考え方を示すガイドブック。 |
| 著者 | 久米 功一 |
| 発売日 | 2020/12/05 |
| 出版社 | 中央経済社 |
| ページ数 | 268ページ |
| 価格 | ¥3,080 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
10位:労働需要の経済学 (叢書・働くということ 第 2巻)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第10位は「労働需要の経済学 (叢書・働くということ 第 2巻)」です。

▼書籍概要
本書は、変化の激しい現代の労働環境について、労働経済学の視点からわかりやすく解説しています。リストラやフリーター、転職といった現代の労働市場の実態を詳述し、賃金や就業形態、労働時間、解雇規制など幅広いテーマを取り上げています。働く人々が将来を見通すための指針となる内容で、変化に適応し、より良い働き方を模索するための重要な情報が満載です。経済の専門家だけでなく、実務に関わる方や労働環境に関心を持つすべての方にとって必読の一冊です。
| 書籍名 | 労働需要の経済学 (叢書・働くということ 第 2巻) |
| 対象者 | 労働市場の変化について理解を深めたいビジネスマンや経済関係者におすすめ。 |
| ひとこと説明 | 労働需要と働き方の変化を理解し、未来の働き方を考えるための基礎知識を提供する一冊。 |
| 著者 | 大橋 勇雄 |
| 発売日 | 2009/06/05 |
| 出版社 | ミネルヴァ書房 |
| ページ数 | 290ページ |
| 価格 | ¥261 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
11位:社会政策 — 福祉と労働の経済学 (有斐閣アルマ)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第11位は「社会政策 — 福祉と労働の経済学 (有斐閣アルマ)」です。

▼書籍概要
本書は、日本の社会政策と労働経済学の最新動向を詳細に解説した一冊です。大規模データ解析を通じて、貧困層の実態や福祉政策の効果を明らかにし、実証的な視点から政策の改善点を提案しています。経済学の専門知識を持つ研究者だけでなく、政策立案者や社会福祉関係者にも役立つ内容が満載です。具体的な事例や統計データを駆使し、現代日本の社会課題に深く切り込む本書は、福祉と労働の経済学を理解したい方にとって貴重な情報源となるでしょう。社会の仕組みと未来を考える上で必読の一冊です。
| 書籍名 | 社会政策 — 福祉と労働の経済学 (有斐閣アルマ) |
| 対象者 | 政策関係者や研究者、福祉・労働分野の専門家におすすめ。 |
| ひとこと説明 | 社会政策と労働経済学の実証分析と政策効果を解説した専門書。 |
| 著者 | 駒村 康平, 山田 篤裕, 四方 理人, 田中 聡一郎, 丸山 桂 |
| 発売日 | 2015/08/29 |
| 出版社 | 有斐閣 |
| ページ数 | 252ページ |
| 価格 | ¥2,650 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
12位:日本の労働市場 — 経済学者の視点
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第12位は「日本の労働市場 — 経済学者の視点」です。

▼書籍概要
本書は、日本の労働市場の現状とその経済的影響を深く掘り下げた実証分析書です。経済学者の視点から、データを駆使して労働制度の変化や雇用形態の多様化、少子高齢化の影響などを解明しています。従来の議論に終止符を打ち、現実に即した根拠ある理解を促す内容となっており、政策立案や経済分析に関心のある読者にとって貴重な資料となるでしょう。日本経済の今後を見通すための重要な一冊です。
| 書籍名 | 日本の労働市場 — 経済学者の視点 |
| 対象者 | 経済研究者や政策担当者、労働市場の実態に関心のあるビジネスパーソンにおすすめ。 |
| ひとこと説明 | 日本の労働市場の実態と経済への影響をデータで解明する本格的研究。 |
| 著者 | 川口 大司 |
| 発売日 | 2017/11/16 |
| 出版社 | 有斐閣 |
| ページ数 | 314ページ |
| 価格 | ¥3,960 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
13位:労働経済学入門 (日経文庫 762 経済学入門シリーズ)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第13位は「労働経済学入門 (日経文庫 762 経済学入門シリーズ)」です。

▼書籍概要
本書は、日本の雇用システムの仕組みや賃金格差、失業の背景について、経済学の基礎知識とともに具体例を交えてわかりやすく解説しています。労働市場の動きや企業の人事戦略、労働者の行動パターンなど、実生活に直結するテーマを丁寧に説明しており、経済の現場を理解したい方に最適です。初心者でも理解しやすい言葉遣いと豊富なケーススタディを通じて、労働経済の全体像をつかむことができる一冊です。
| 書籍名 | 労働経済学入門 (日経文庫 762 経済学入門シリーズ) |
| 対象者 | 経済や労働市場の動きに関心があるビジネスマンやマネージャーにおすすめ。 |
| ひとこと説明 | 日本の労働経済の仕組みと現実の動きが具体例とともに学べる入門書。 |
| 著者 | 大竹 文雄 |
| 発売日 | 1998/04/01 |
| 出版社 | 日本経済新聞出版 |
| ページ数 | 210ページ |
| 価格 | ¥125 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
14位:キャリアと労働の経済学[第2版]
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第14位は「キャリアと労働の経済学[第2版]」です。
![キャリアと労働の経済学[第2版]](https://m.media-amazon.com/images/I/31i3dGxug8L._SL500_.jpg)
▼書籍概要
本書は、労働市場や雇用形態、賃金形成、労働供給と需要など、キャリア形成と労働経済の基本的な仕組みを丁寧に解説しています。経済学の理論と実際の労働市場の動向を結びつけ、企業と労働者の関係性や政策の影響を理解できる内容となっています。特に、労働市場の変化や働き方改革に関心のあるビジネスパーソンや経済研究者にとって、実務や研究の両面で役立つ一冊です。データ分析や最新の労働経済学のトピックも取り入れ、現代の労働環境を深く理解できる内容になっています。
| 書籍名 | キャリアと労働の経済学[第2版] |
| 対象者 | 労働経済やキャリア戦略に関心のあるビジネスパーソンや経済研究者におすすめ。 |
| ひとこと説明 | 労働市場の仕組みとキャリア形成を体系的に理解できる労働経済学の解説書。 |
| 著者 | 小﨑 敏男, 牧野 文夫, 吉田 良生, 小﨑 敏男, 牧野 文夫, 吉田 良生 |
| 発売日 | 2022/03/14 |
| 出版社 | 日本評論社 |
| ページ数 | 不明 |
| 価格 | ¥2,860 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
15位:労働経済学入門-新しい働き方の実現を目指して
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第15位は「労働経済学入門-新しい働き方の実現を目指して」です。

▼書籍概要
本書は、現代の多様な働き方や労働市場の変化を踏まえた新しい労働経済学の基礎と応用を解説した一冊です。働き方改革やフリーランスの増加、非正規雇用の拡大など、最新の動向をわかりやすく整理し、労働経済の基本的な理論とともに社会的な背景も丁寧に解説しています。実務や政策立案に役立つだけでなく、働き方の未来像を考える上でも貴重な資料となるでしょう。専門的な内容を初心者にも理解しやすく構成しており、現代の働き方に関心がある方にとって必読の一冊です。
| 書籍名 | 労働経済学入門-新しい働き方の実現を目指して |
| 対象者 | 経営者、政策立案者、労働研究者、労働市場に関心のある実務者向け |
| ひとこと説明 | 現代の働き方と労働市場の変化を理解するための労働経済学の実践的入門書。 |
| 著者 | 脇坂明 |
| 発売日 | 2011/12/09 |
| 出版社 | 日本評論社 |
| ページ数 | 186ページ |
| 価格 | ¥2,640 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
16位:仕事の経済学
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第16位は「仕事の経済学」です。

▼書籍概要
本書は、経済学の基礎から応用までを深く掘り下げ、特に「知的熟練」と「長期的競争」に重点を置いた著者の独自の視点を展開しています。豊富な統計データや資料を駆使し、理論と実例をバランスよく解説しているため、経済の実態や動向を体系的に理解したいビジネスパーソンや経済研究者にとって非常に有益な一冊です。長年にわたり改訂を重ね、最新テーマも盛り込むことで、現代の経済状況に即した内容になっています。経済の本質を理解し、実務や戦略に役立てたい方におすすめです。
| 書籍名 | 仕事の経済学 |
| 対象者 | 経済やビジネスの実務に関心がある専門家や研究者、経営者に最適。 |
| ひとこと説明 | 経済の現状と長期的競争戦略を理解するための体系的なガイドブック。 |
| 著者 | 小池 和男 |
| 発売日 | 2005/02/01 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| ページ数 | 364ページ |
| 価格 | ¥3,520 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
17位:労働力不足の経済学 日本経済はどう変わるか
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第17位は「労働力不足の経済学 日本経済はどう変わるか」です。

▼書籍概要
本書は、日本経済における深刻な労働力不足の現状とその影響を解説した労働経済学の入門書です。2011年版からの社会変化や制度改正、最新のデータを反映し、少子高齢化や働き方改革などの要因がどのように経済に影響を及ぼしているかを丁寧に解説しています。激動する社会の中で、今後の経済の動向や企業の戦略、政策立案に役立つ具体的な知見を得られる一冊です。経済の動きと社会の変化を理解し、未来を見通す力を養いたい方におすすめです。
| 書籍名 | 労働力不足の経済学 日本経済はどう変わるか |
| 対象者 | 経済・労働政策に関心のあるビジネスパーソンや研究者向け。 |
| ひとこと説明 | 労働力不足と日本経済の未来を理解するための実践的な解説書。 |
| 著者 | 小﨑 敏男 |
| 発売日 | 2018/02/13 |
| 出版社 | 日本評論社 |
| ページ数 | 288ページ |
| 価格 | ¥3,190 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
18位:なぜ働いても豊かになれないのか マルクスと考える資本と労働の経済学 (角川ソフィア文庫)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第18位は「なぜ働いても豊かになれないのか マルクスと考える資本と労働の経済学 (角川ソフィア文庫)」です。

▼書籍概要
本書は、資本主義経済の根底にある資本と労働の関係性を、マルクスの思想を通じて深く掘り下げた一冊です。現代社会で頻繁に取りざたされるパワハラや過労死、職場うつといった労働環境の問題に対し、なぜ人々が過酷な労働を続けるのか、その背景にある資本主義の構造的な問題を明らかにします。著者はマルクスの理論を現代の経済システムに照らしながら、私たちの暮らしがより豊かになるための課題と解決策を模索します。働くことの意味や経済格差の根源について深く考えたい読者にとって、重要な視点を提供してくれる一冊です。
| 書籍名 | なぜ働いても豊かになれないのか マルクスと考える資本と労働の経済学 (角川ソフィア文庫) |
| 対象者 | 資本主義経済や労働問題に関心のある社会人や経済学・社会学に興味がある方におすすめです。 |
| ひとこと説明 | 資本と労働の関係をマルクスの視点から解き明かし、現代の労働問題の根源に迫る経済学書。 |
| 著者 | 佐々木 隆治 |
| 発売日 | 2025/01/24 |
| 出版社 | KADOKAWA |
| ページ数 | 158ページ |
| 価格 | ¥1,100 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
19位:労働経済
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第19位は「労働経済」です。

▼書籍概要
本書は、現代の労働市場で急速に進展している女性の雇用拡大や高齢者の働き方、多様化する働き方を取り上げ、経済学の視点から解説しています。特に第四次産業革命による新たな労働環境や働き方の変化について、具体例やデータを交えながらわかりやすく解説しているため、労働政策や経済動向に関心がある方にとって必読の一冊です。現代の労働問題の背景や解決策を理解し、未来の労働市場について考えるきっかけとなる内容となっています。
| 書籍名 | 労働経済 |
| 対象者 | 経済・労働政策に関心のある専門家やビジネスパーソン向け |
| ひとこと説明 | 現代の労働市場の課題と変化を経済学の観点から詳しく解説した実践的な解説書。 |
| 著者 | 清家 篤, 風神 佐知子 |
| 発売日 | 2020/09/18 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| ページ数 | 321ページ |
| 価格 | ¥1,694 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
20位:基本講義 労働経済学 (ライブラリ経済学基本講義 9)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第20位は「基本講義 労働経済学 (ライブラリ経済学基本講義 9)」です。

▼書籍概要
本書は、労働経済学の基礎から応用までをわかりやすく解説した入門書です。身近なアルバイトや就職活動の具体例を通じて問題意識を喚起し、その後の理論的解説へとスムーズに導きます。実務や政策に関わる方だけでなく、経済学を初めて学ぶ方にも理解しやすい構成となっており、労働市場の仕組みや動向を深く理解したい方に最適です。図表や事例も豊富で、学習意欲を引き出す工夫が随所に施されています。
| 書籍名 | 基本講義 労働経済学 (ライブラリ経済学基本講義 9) |
| 対象者 | 実務関係者や経済学の基礎を学ぶビジネスパーソンにおすすめです。 |
| ひとこと説明 | 労働経済学の基本を身近な事例と理論で理解できる入門書です。 |
| 著者 | 阿部 正浩 |
| 発売日 | 2021/11/25 |
| 出版社 | 新世社 |
| ページ数 | 296ページ |
| 価格 | ¥3,360 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
21位:経済学の思考軸 ――効率か公平かのジレンマ (ちくま新書 1791)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第21位は「経済学の思考軸 ――効率か公平かのジレンマ (ちくま新書 1791)」です。

▼書籍概要
本書は、経済学の基本的な視点である「個人の幸せ」を出発点としながらも、社会全体の理想や未来像をどのように議論できるのかを深掘りしています。効率と公平という二つの評価軸を軸に、少子高齢化や人口減少といった日本社会の課題に対する経済運営のあり方を丁寧に考察。現代の経済学が抱えるジレンマや、その解決に向けた示唆を示す一冊です。政策立案者や経済関係者だけでなく、社会の未来を考える読者にも新たな視点をもたらす内容となっています。
| 書籍名 | 経済学の思考軸 ――効率か公平かのジレンマ (ちくま新書 1791) |
| 対象者 | 政策や経済の課題に関心のある社会人や研究者向け。 |
| ひとこと説明 | 効率と公平の観点から現代社会の経済運営を考える新しい視点の本。 |
| 著者 | 小塩 隆士 |
| 発売日 | 2024/05/10 |
| 出版社 | 筑摩書房 |
| ページ数 | 不明 |
| 価格 | ¥990 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
22位:賃労働と資本 (岩波文庫 白 124-6)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第22位は「賃労働と資本 (岩波文庫 白 124-6)」です。

▼書籍概要
本書は、カール・マルクスの『賃労働と資本』を通じて、資本主義経済の根本的な仕組みとその歴史的背景を解明した重要な古典的名著です。労働と資本の基本概念、利潤の源泉、賃金の本質について、古典派経済学と対話しながら論理的に展開しています。付録や詳細な解説も充実しており、『資本論』の理解を深める入門書として最適です。経済学や社会構造に関心がある方にとって、資本主義の本質を理解する絶好の書です。
| 書籍名 | 賃労働と資本 (岩波文庫 白 124-6) |
| 対象者 | 経済学や社会構造の深い理解に関心のある、研究者やビジネスパーソンにおすすめ。 |
| ひとこと説明 | 資本主義の基本原理と労働・資本の関係性を解明した、マルクス経済学の入門書。 |
| 著者 | カール マルクス, Marx,Karl, 文雄, 長谷部 |
| 発売日 | 1981/07/16 |
| 出版社 | 岩波書店 |
| ページ数 | 412ページ |
| 価格 | ¥627 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
23位:なぜ子どもの将来に両親が重要なのか:家族格差の経済学
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第23位は「なぜ子どもの将来に両親が重要なのか:家族格差の経済学」です。

▼書籍概要
本書は、子どもの将来において家庭環境や親の経済状況がいかに重要かを解明した、経済学の視点から家族格差を分析した一冊です。親の教育資産や経済的安定性が子どもの学力向上や社会的成功に直結している事実を、多くの実証データとともに示しています。子どもたちの将来を左右する家庭の役割について深く理解でき、政策提言や教育の在り方についても考えさせられる内容です。家庭の経済格差が社会全体の未来にどのような影響を与えるのか、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説しています。
| 書籍名 | なぜ子どもの将来に両親が重要なのか:家族格差の経済学 |
| 対象者 | 家族の経済状況や教育格差に関心のある経済学者や政策立案者、教育関係者向け。 |
| ひとこと説明 | 子どもの将来に家庭の経済的背景がどれほど影響するかを解明した、家族格差の経済学の解説書。 |
| 著者 | メリッサ・S・カーニー, 鹿田昌美 |
| 発売日 | 2025/04/10 |
| 出版社 | 慶應義塾大学出版会 |
| ページ数 | 不明 |
| 価格 | ¥3,520 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
24位:日本的雇用慣行の経済学: 労働市場の流動化と日本経済
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第24位は「日本的雇用慣行の経済学: 労働市場の流動化と日本経済」です。

▼書籍概要
本書は、日本の雇用慣行の特徴とその経済的影響に焦点を当て、労働市場の流動化や長期雇用の仕組みが日本経済に与える役割を深く解説しています。労働市場の硬直性や企業の雇用戦略、賃金制度の背景を実証的に分析し、日本経済の持続的成長や構造的課題を理解するための貴重な一冊です。経済学の視点から日本の雇用文化を解き明かすことで、政策立案者や経営者だけでなく、経済の動きに関心のある読者にも役立ちます。労働市場の流動性向上や制度改革の必要性についての洞察も得られるでしょう。
| 書籍名 | 日本的雇用慣行の経済学: 労働市場の流動化と日本経済 |
| 対象者 | 日本の労働市場や雇用制度に関心のある経済関係者や研究者におすすめ。 |
| ひとこと説明 | 日本の雇用慣行と労働市場の流動化を経済学的に分析した専門書。 |
| 著者 | 八代 尚宏 |
| 発売日 | 1997/01/01 |
| 出版社 | 日本経済新聞出版 |
| ページ数 | 286ページ |
| 価格 | ¥71 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
25位:労働の経済学: 少子高齢社会の労働政策を探る
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第25位は「労働の経済学: 少子高齢社会の労働政策を探る」です。

▼書籍概要
本書は、少子高齢社会における日本の労働経済の現状と課題を詳細に分析した一冊です。若年労働力の減少や高齢者の増加、女性や外国人労働者の労働参加の拡大といった供給側の変化、さらに3次産業の拡大や非正規雇用の増加、雇用調整や労働時間の短縮といった需要側の動きに焦点を当て、それらがもたらす経済的・社会的な影響を浮き彫りにしています。労働政策の方向性や解決策についても具体的に提言しており、経済学的な視点から現代の労働問題を理解したい方に最適です。学術的な深さと実務的な視点の両面を兼ね備えた内容となっています。
| 書籍名 | 労働の経済学: 少子高齢社会の労働政策を探る |
| 対象者 | 労働経済や社会保障制度に関心のある政策立案者や研究者におすすめです。 |
| ひとこと説明 | 少子高齢化と労働市場の変化を理解し、未来の労働政策を考えるための重要な一冊。 |
| 著者 | 笹島 芳雄 |
| 発売日 | 2009/03/01 |
| 出版社 | 中央経済グループパブリッシング |
| ページ数 | 225ページ |
| 価格 | ¥806 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
26位:労働市場改革の経済学
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第26位は「労働市場改革の経済学」です。

▼書籍概要
本書は、日本の労働市場における構造的な問題とその改革の方向性について、経済学の観点から鋭く分析しています。特に、民主党政権が進めた派遣労働の規制強化策がワーキングプアの解消に効果的でないことを指摘し、実効性のある労働格差解消策を提案しています。労働市場の仕組みや政策の影響を理解したい経営者や政策担当者にとって、現実的な解決策を模索するための重要な知見を提供します。経済学と労働政策の融合による深い洞察が詰まった一冊です。
| 書籍名 | 労働市場改革の経済学 |
| 対象者 | 労働政策や経済学に関心のある企業経営者や政策立案者におすすめ。 |
| ひとこと説明 | 労働市場の構造と格差解消のための実践的な経済学の解説書。 |
| 著者 | 八代 尚宏 |
| 発売日 | 2009/11/20 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| ページ数 | 288ページ |
| 価格 | ¥2,420 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
27位:労働経済学 (プログレッシブ経済学シリーズ)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第27位は「労働経済学 (プログレッシブ経済学シリーズ)」です。

▼書籍概要
本書は労働経済学の基礎から応用までを網羅した一冊であり、労働市場の動向や賃金形成、雇用政策の経済的背景について詳しく解説しています。労働供給と需要の関係、労働市場の構造変化、非正規雇用の増加など、現代の労働経済を理解するために必要な理論と実証データを豊富に含んでいます。実務や研究、政策立案に携わる方々にとって、実用的な知識と深い洞察を提供し、労働市場の動向を正確に捉えるための重要な手引きとなるでしょう。経済学の専門知識を持つ読者にとっても、新たな視点や分析方法を得られる内容となっています。
| 書籍名 | 労働経済学 (プログレッシブ経済学シリーズ) |
| 対象者 | 労働市場の実態と経済的背景に関心のある専門家や研究者におすすめ。 |
| ひとこと説明 | 労働経済学の基本理論と現代の労働市場の動向を理解するための重要な解説書。 |
| 著者 | 樋口 美雄 |
| 発売日 | 1996/02/01 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| ページ数 | 394ページ |
| 価格 | ¥3,190 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
28位:労働経済学[文庫本](中国語版)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第28位は「労働経済学[文庫本](中国語版)」です。
](https://m.media-amazon.com/images/I/41zcolZiLdL._SL500_.jpg)
▼書籍概要
本書は、労働経済学の基礎から最新の研究動向までを中国語で解説した一冊です。労働市場の仕組み、賃金形成、雇用政策、労働供給と需要の関係性など、多角的な視点から分析されています。実証データやケーススタディも豊富に盛り込まれており、実務に役立つ知識を深めたい専門家や実務者にとって貴重な資料となります。中国の労働市場の現状や変化を理解し、経済政策や企業戦略に活かすヒントが詰まっています。難解になりすぎず、理論と実践をバランス良く解説している点も魅力です。
| 書籍名 | 労働経済学[文庫本](中国語版) |
| 対象者 | 経済・労働政策に関心のある専門職や研究者向け |
| ひとこと説明 | 労働経済学の基礎と最新動向を中国語で学べる解説書。 |
| 著者 | 著者情報なし |
| 発売日 | 不明 |
| 出版社 | 不明 |
| ページ数 | 不明 |
| 価格 | ¥4,690 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
29位:なぜ男女の賃金に格差があるのか:女性の生き方の経済学
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第29位は「なぜ男女の賃金に格差があるのか:女性の生き方の経済学」です。

▼書籍概要
本書は、先進国アメリカにおいても依然として存在する男女賃金格差の背景を、歴史的な社会変革や政策の変遷を交えて分析した一冊です。女性の「家族」と「仕事」の選択が賃金格差にどう影響しているのかを、経済学の視点から丁寧に解き明かしています。ウーマンリブや静かな革命といった社会運動の歴史や、公平賃金法の効果も詳細に検討し、現代社会での働き方や性別平等を考えるための重要な示唆を提供します。男女の賃金格差の根本原因を理解し、より公平な労働環境の構築に向けた一助となるでしょう。
| 書籍名 | なぜ男女の賃金に格差があるのか:女性の生き方の経済学 |
| 対象者 | 男女の賃金格差や働き方に関心がある経済・社会問題の専門家や政策立案者におすすめ。 |
| ひとこと説明 | 社会歴史と経済分析を通じて、男女賃金格差の本質と解決策を明らかにする一冊。 |
| 著者 | クラウディア・ゴールディン |
| 発売日 | 2023/03/31 |
| 出版社 | 慶應義塾大学出版会 |
| ページ数 | 311ページ |
| 価格 | ¥3,740 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
30位:働くことの経済学 (有斐閣ブックス 401)
労働経済学のおすすめ本・書籍ランキングの第30位は「働くことの経済学 (有斐閣ブックス 401)」です。

▼書籍概要
本書は、労働の多面的な側面を経済学の視点からわかりやすく解説した入門書です。働くことの意味や働き方の多様性、経済現象との関係性を丁寧に説明し、労働市場の仕組みや労働者の行動を理解するための基礎知識を提供します。単なる仕事の経済学だけでなく、自己実現や社会的役割など働くことの深い意義にも触れており、労働に関心のある方やビジネスの現場で働く方にとって役立つ内容です。読みやすさと実用性を兼ね備えた一冊で、労働の本質を理解したい方に特におすすめします。
| 書籍名 | 働くことの経済学 (有斐閣ブックス 401) |
| 対象者 | 労働経済学に興味があるビジネスパーソンや実務者向け。 |
| ひとこと説明 | 働くことの経済学をわかりやすく解説し、労働市場や働き方の本質を理解させる入門書。 |
| 著者 | 古郡 鞆子 |
| 発売日 | 1998/05/01 |
| 出版社 | 有斐閣 |
| ページ数 | 240ページ |
| 価格 | ¥15 |
| 読んだ人のクチコミ |
|
